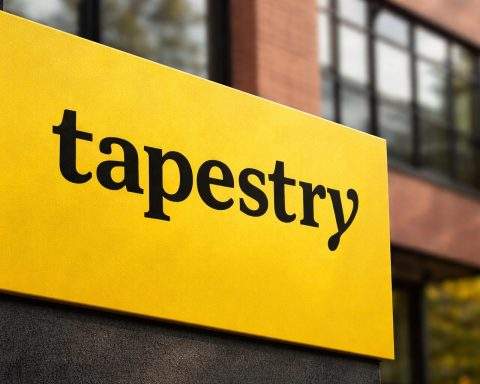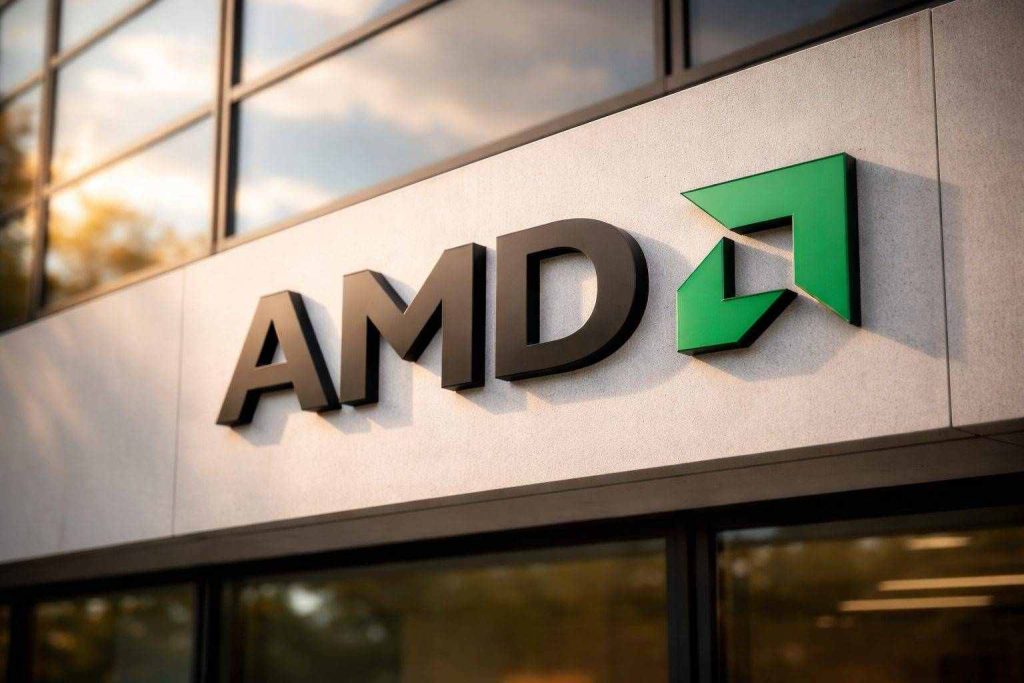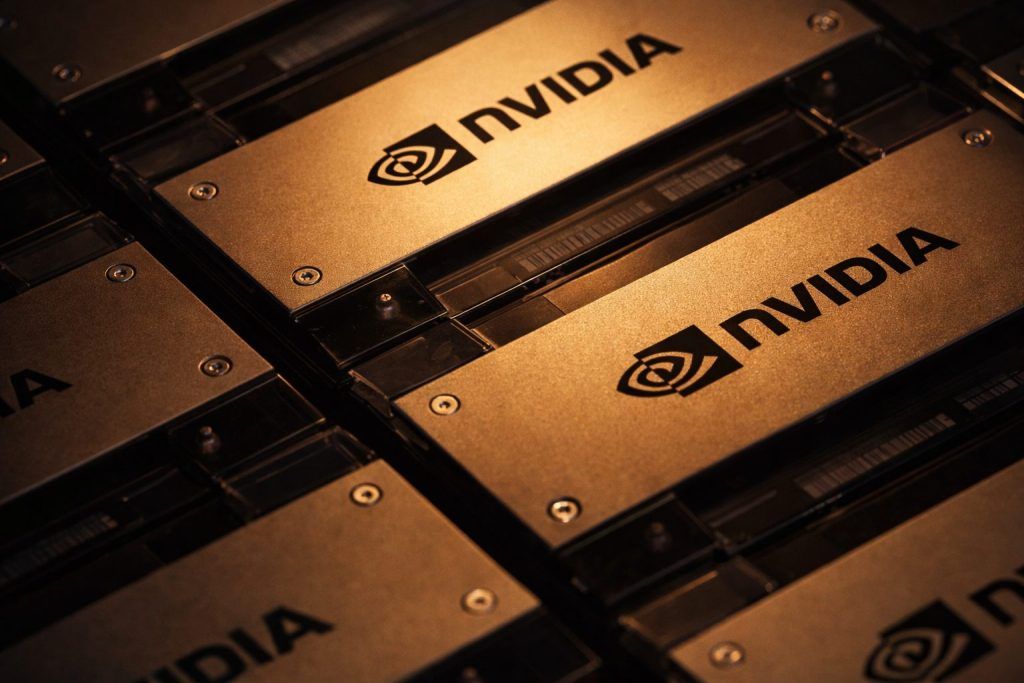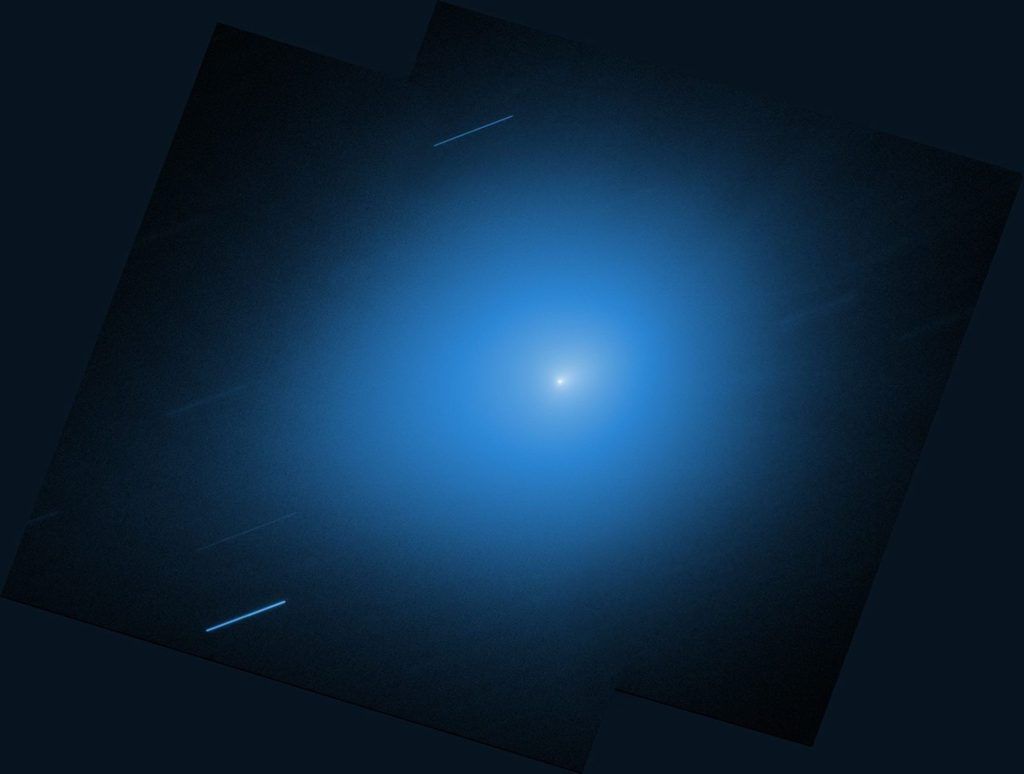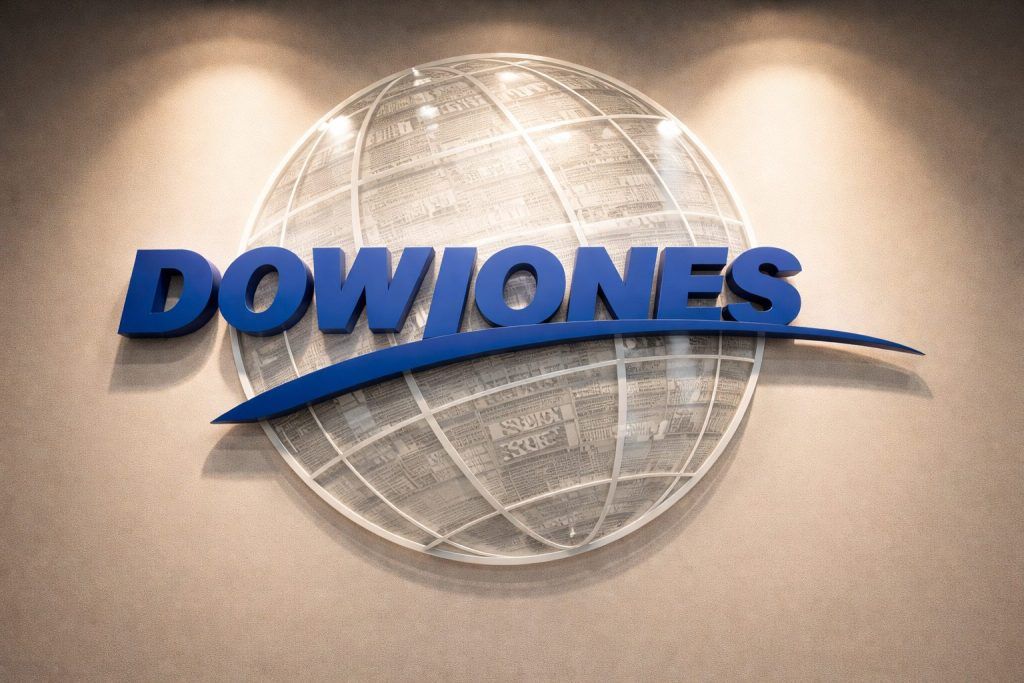Kein IRS-Stimulus-Scheck über 2.000 Dollar kommt im Februar 2026 – aber Trumps Gerede über Zoll-Schecks hält die Gerüchte am Leben
Für Februar 2026 sind keine neuen bundesweiten Stimulus-Schecks geplant, der IRS hat keine Ankündigung gemacht und der Kongress keine Zahlungen genehmigt. Trump prüft laut NBC $2.000 Tarif-Rabatt-Schecks, hat sich aber nicht festgelegt. Der IRS warnt vor Betrugsversuchen per SMS oder E-Mail. Social-Media-Gerüchte über neue Schecks halten an.