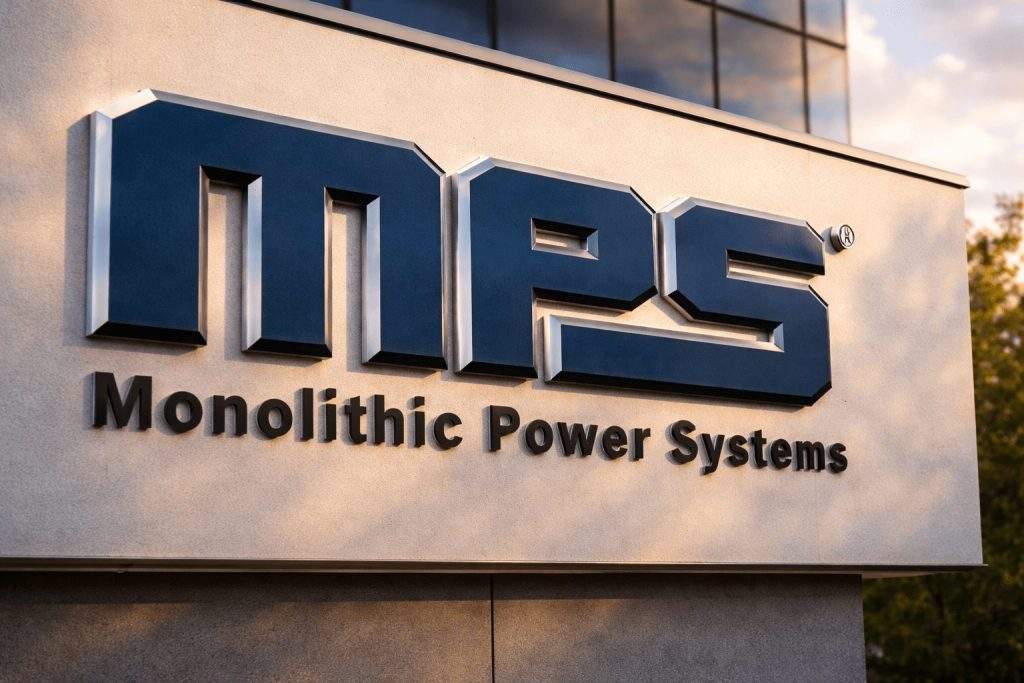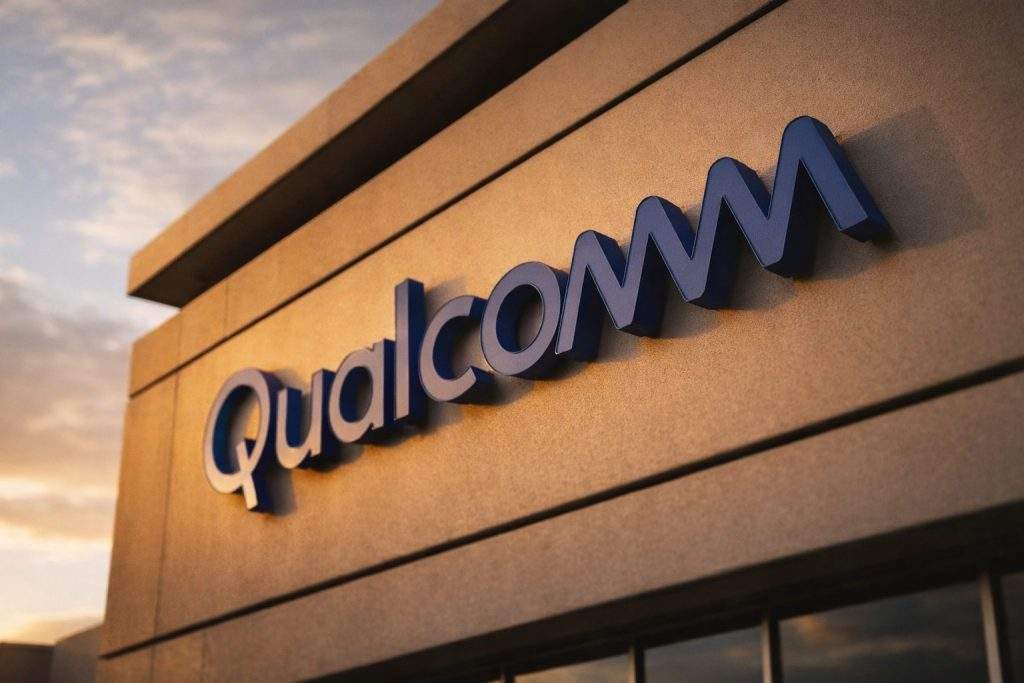Tower Semiconductor stock jumps again on Nvidia optics tie-up as earnings near
Tower Semiconductor shares rose 7.7% to $139.04 Friday after announcing a collaboration with Nvidia on AI data-center networking. The stock touched $141 intraday and gained another 1% after hours. Investors await Tower’s Feb. 11 earnings for details on its silicon photonics work. No financial terms or shipment timeline were disclosed.