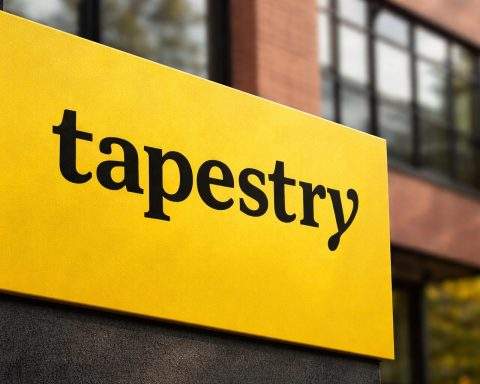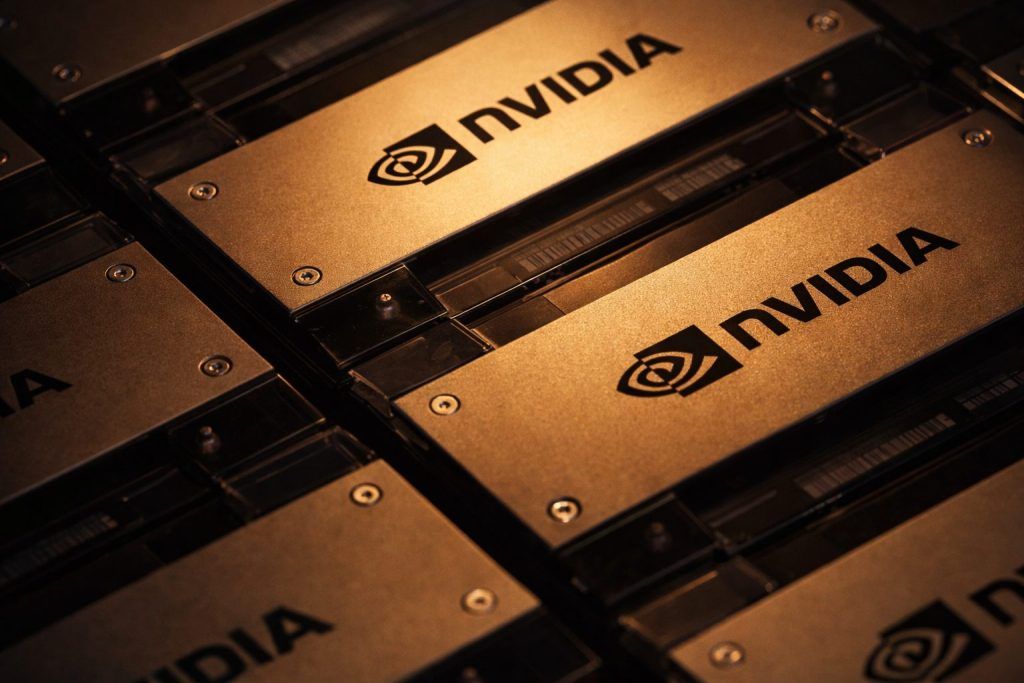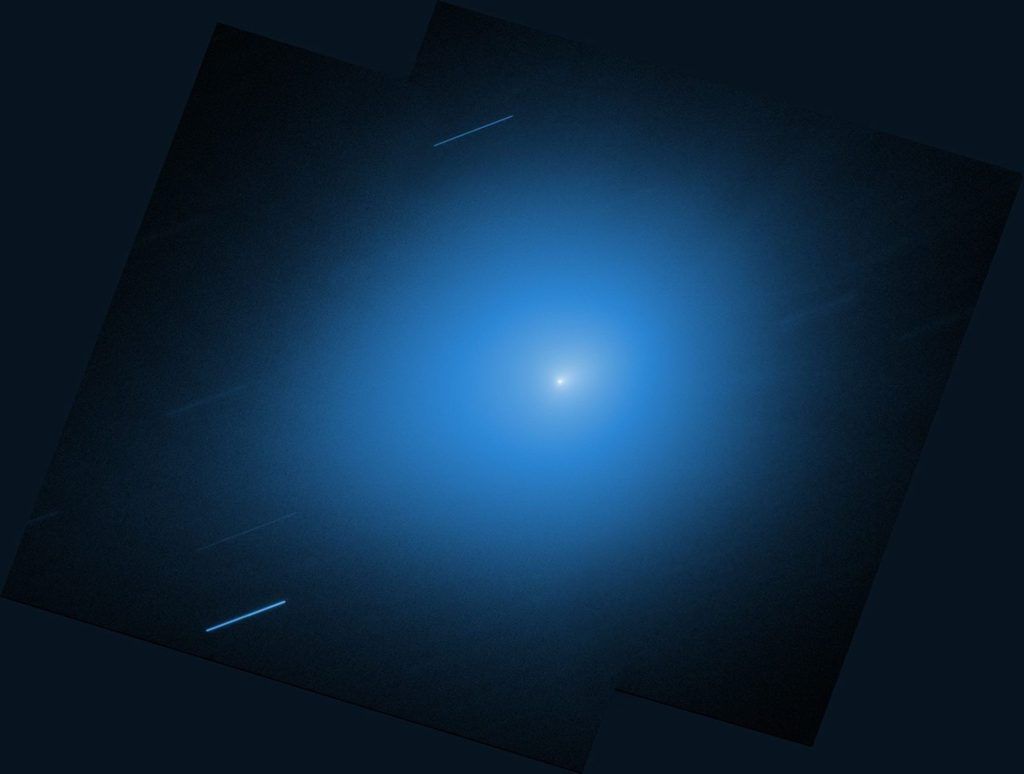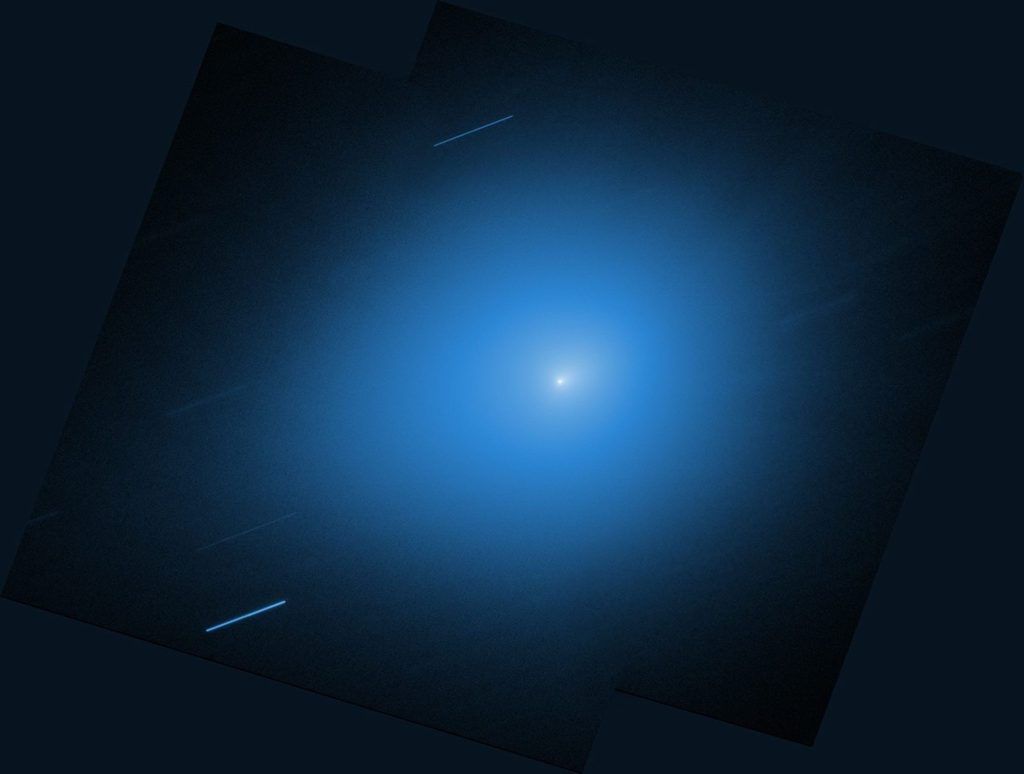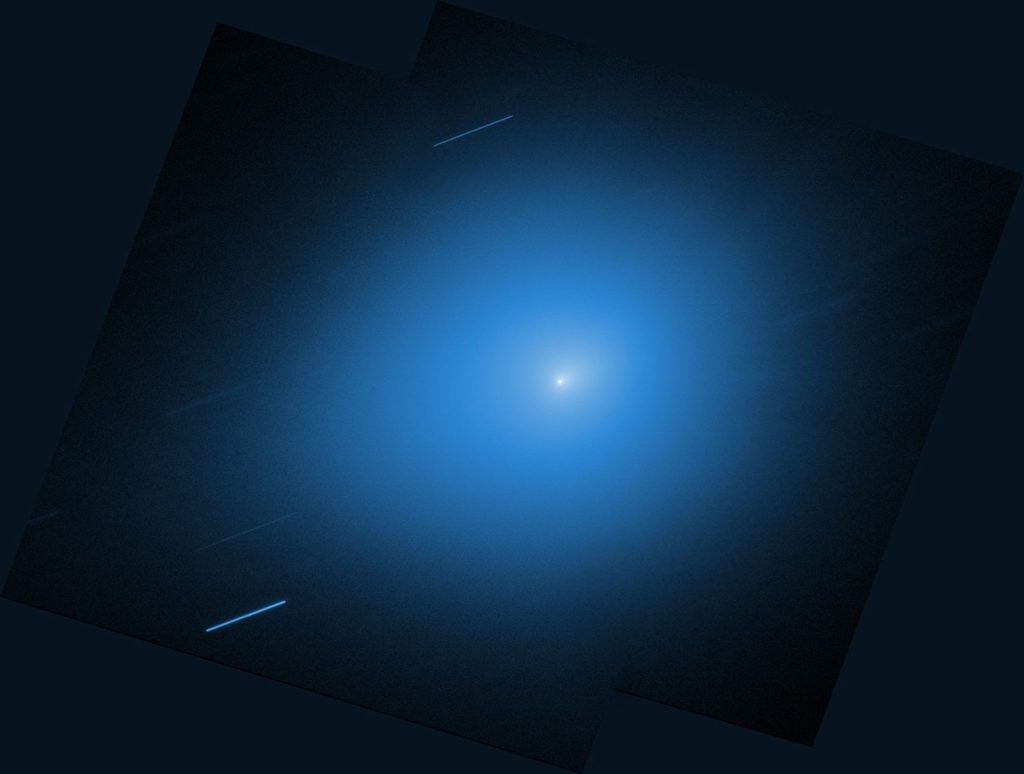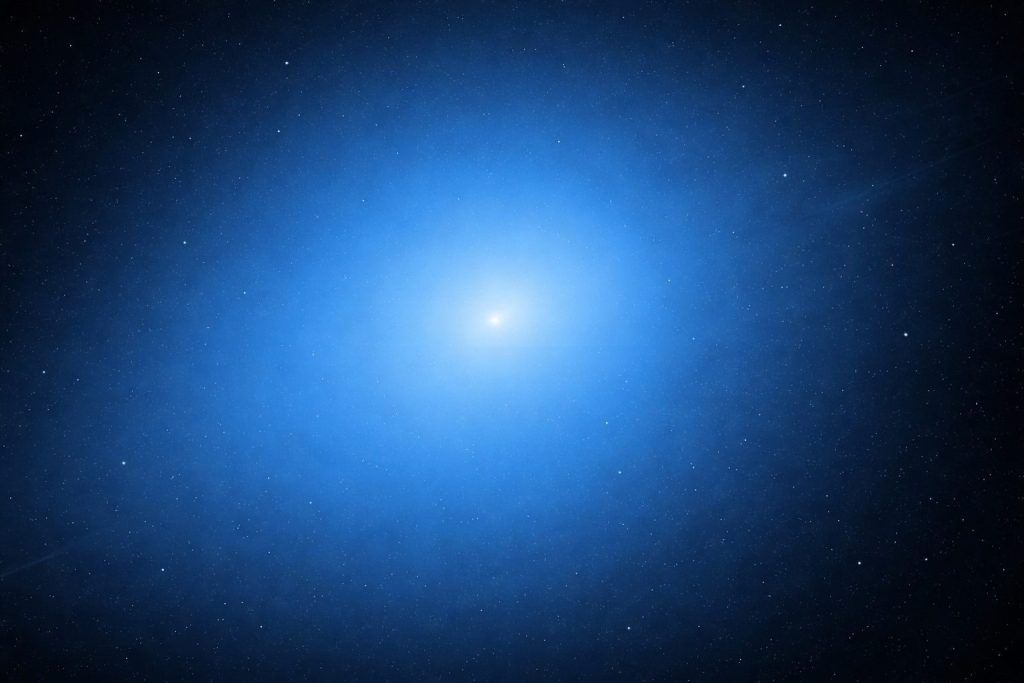Micron-aandeel daalt na bericht dat Nvidia HBM4-bestellingen mogelijk naar SK Hynix en Samsung gaan
Het aandeel Micron daalde vrijdag 0,5% in de voorbeurshandel nadat Semianalysis voorspelde dat Micron geen HBM4-geheugen aan Nvidia zal leveren. SK Hynix en Samsung nemen volgens analisten respectievelijk 70% en 30% van Nvidia’s HBM4-orders voor hun rekening.