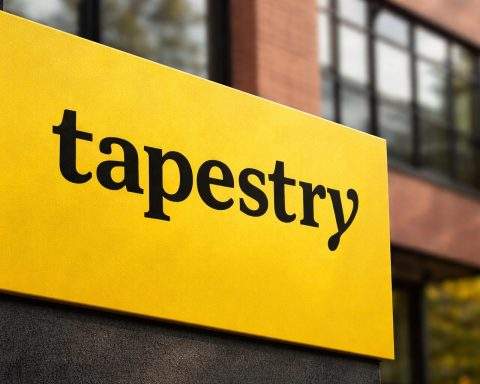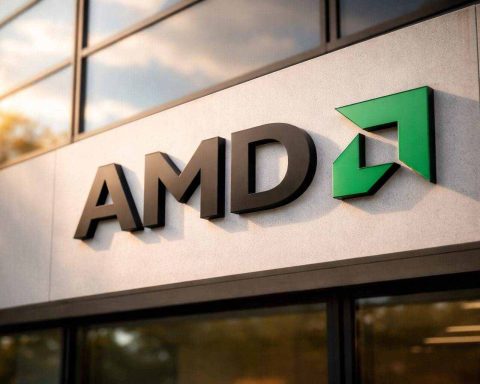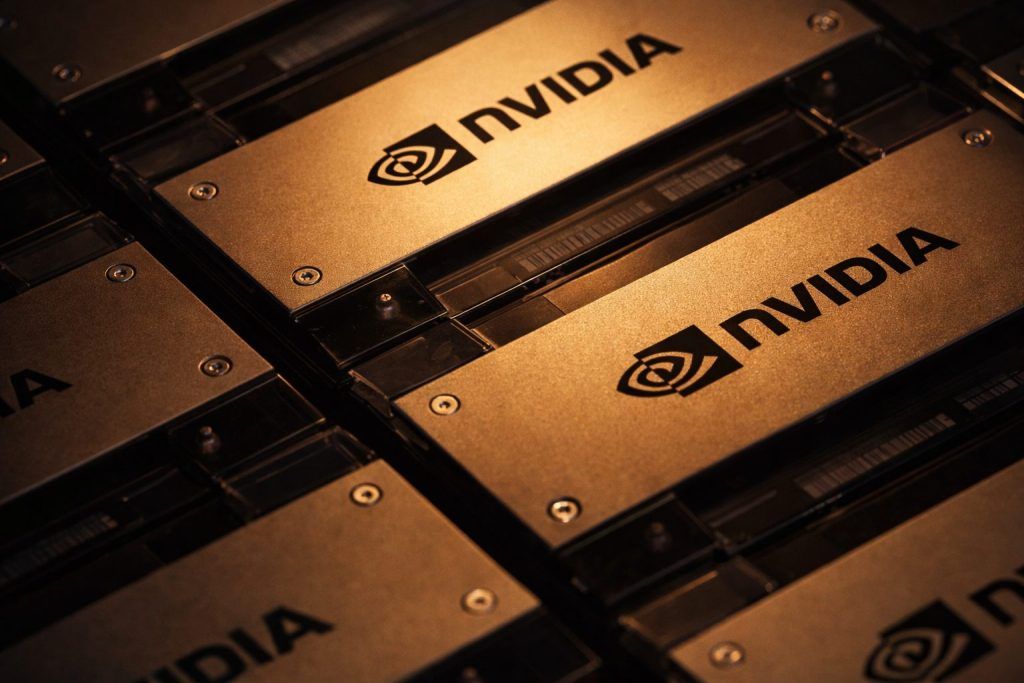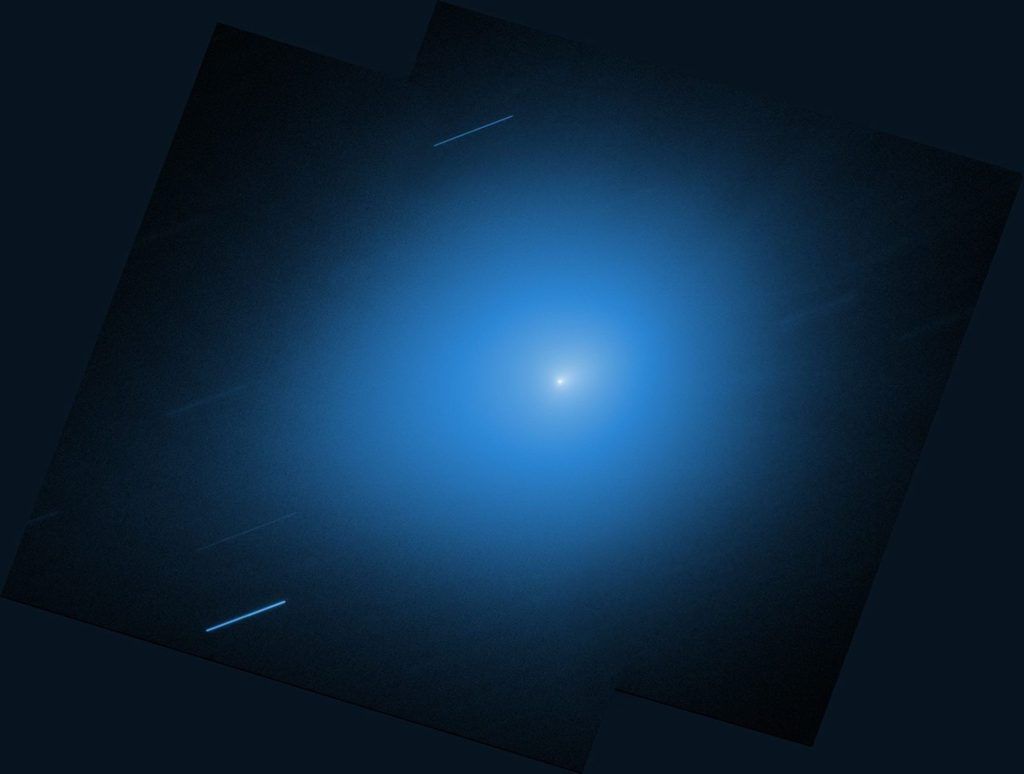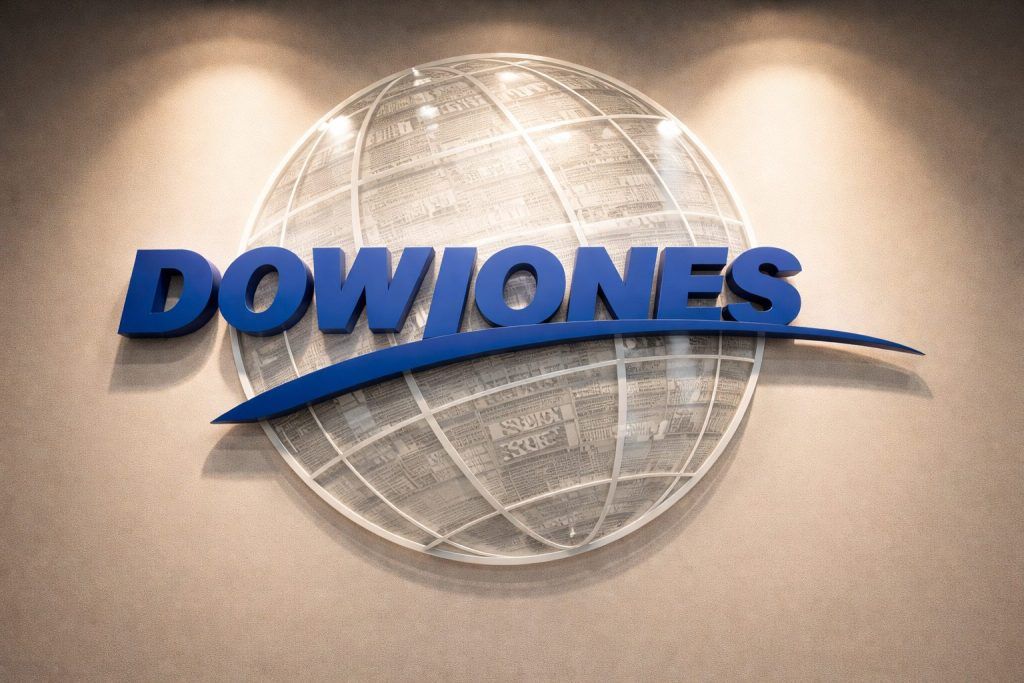Nie będzie czeku stymulacyjnego IRS na 2000 dolarów w lutym 2026 roku — ale rozmowy Trumpa o „czekach z ceł” podtrzymują plotki
Nie przewidziano nowych federalnych czeków stymulacyjnych na luty 2026—IRS i Kongres nie ogłosili żadnych wypłat. Donald Trump powiedział NBC, że „rozważa” czeki zwrotne z ceł, ale nie zobowiązał się do ich wprowadzenia. IRS ostrzega przed fałszywymi SMS-ami i e-mailami obiecującymi płatności stymulacyjne.