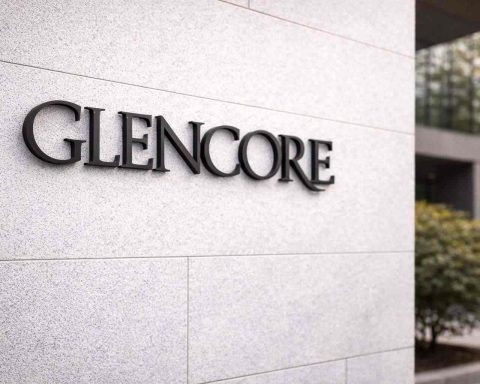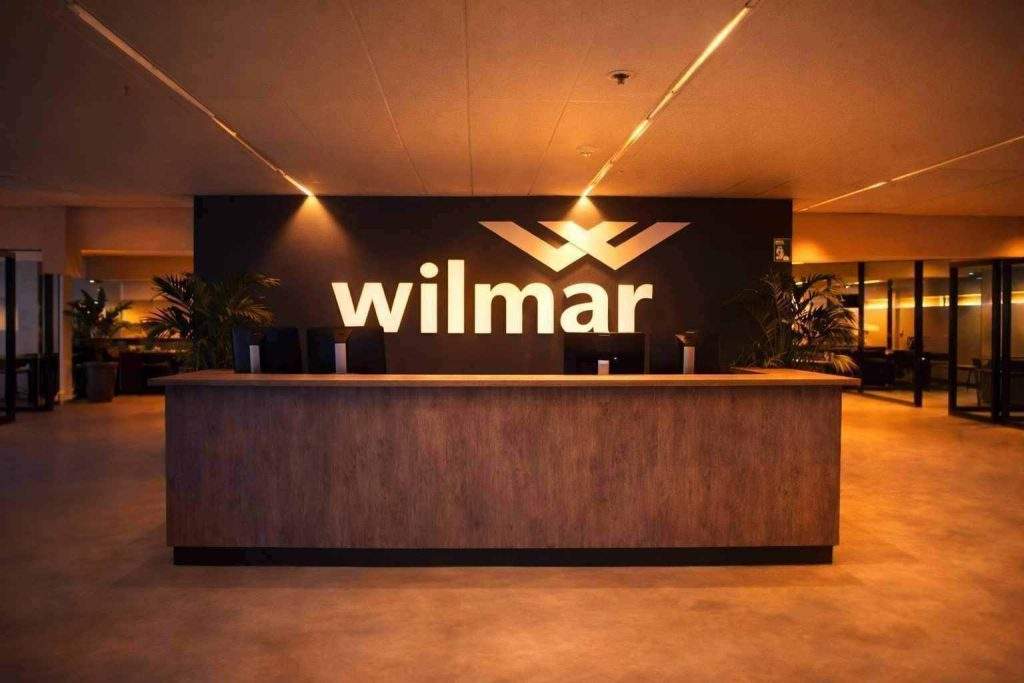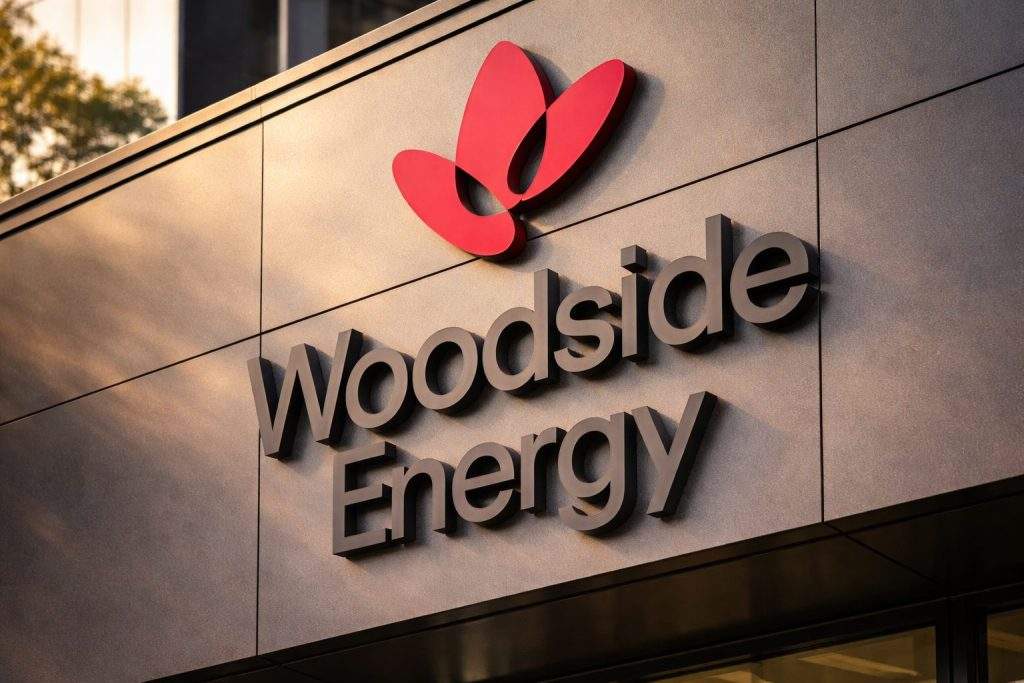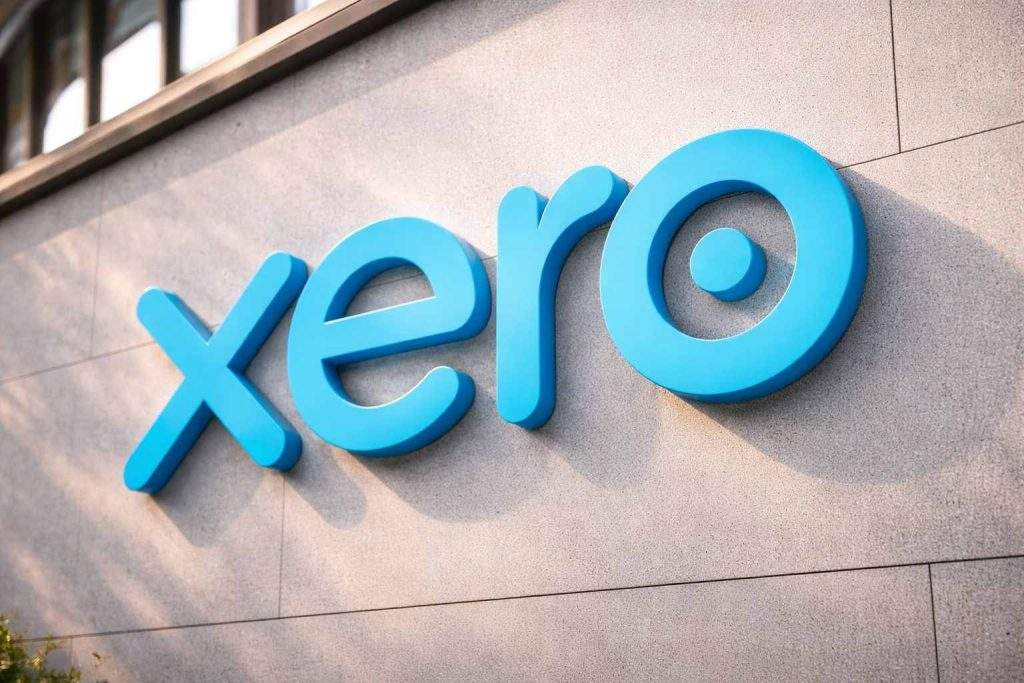BAT stock ends week higher as buyback rolls on; investors eye Feb 12 results
British American Tobacco shares closed up 1.2% at 4,609 pence on Friday, outpacing the FTSE 100 ahead of its preliminary results due Feb. 12. The company bought back 121,668 shares this week for cancellation. CEO Tadeu Marroco received 364 shares under a bonus scheme. Investors are watching for updates on BAT’s nicotine alternatives and sector competition after Philip Morris International’s latest results.