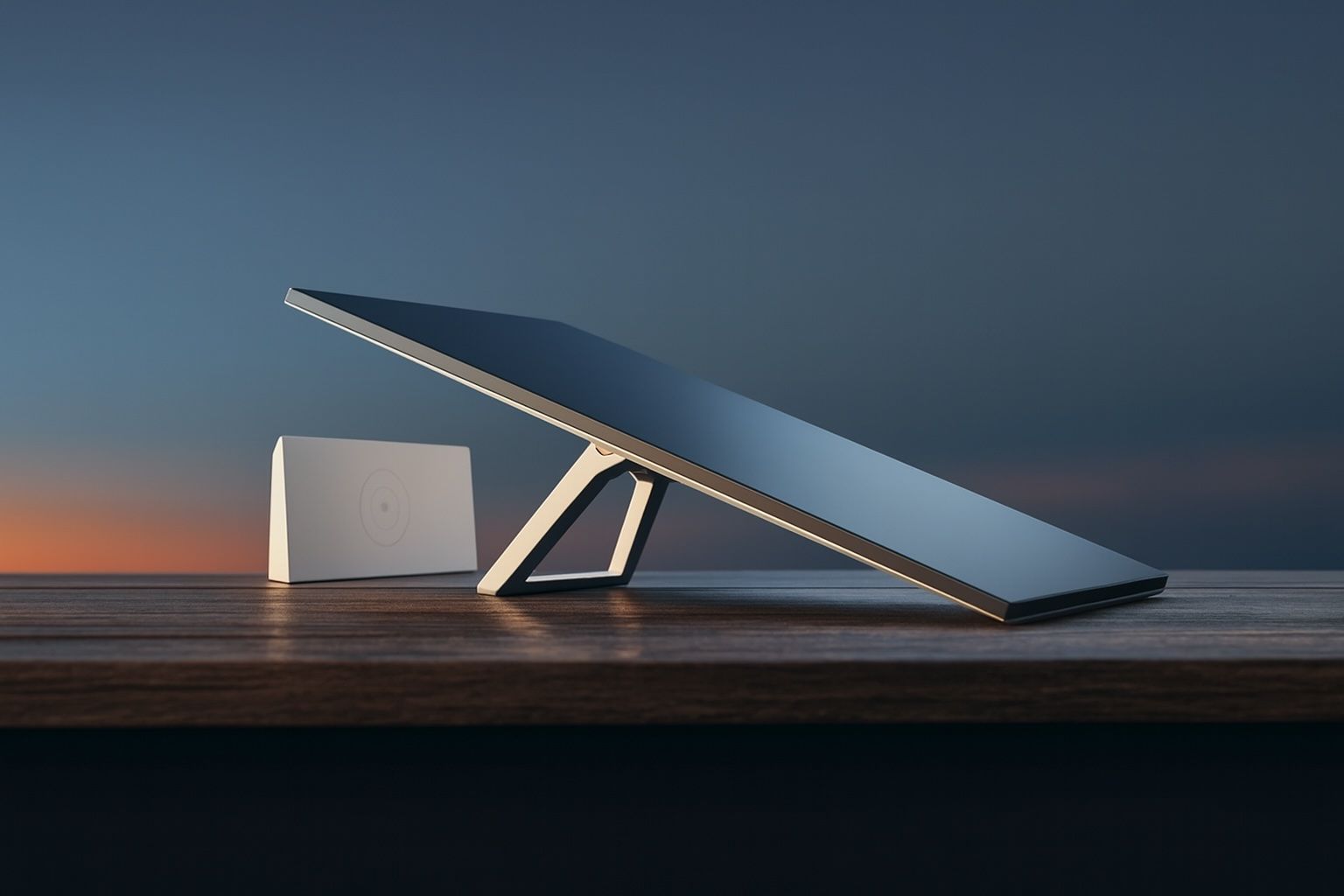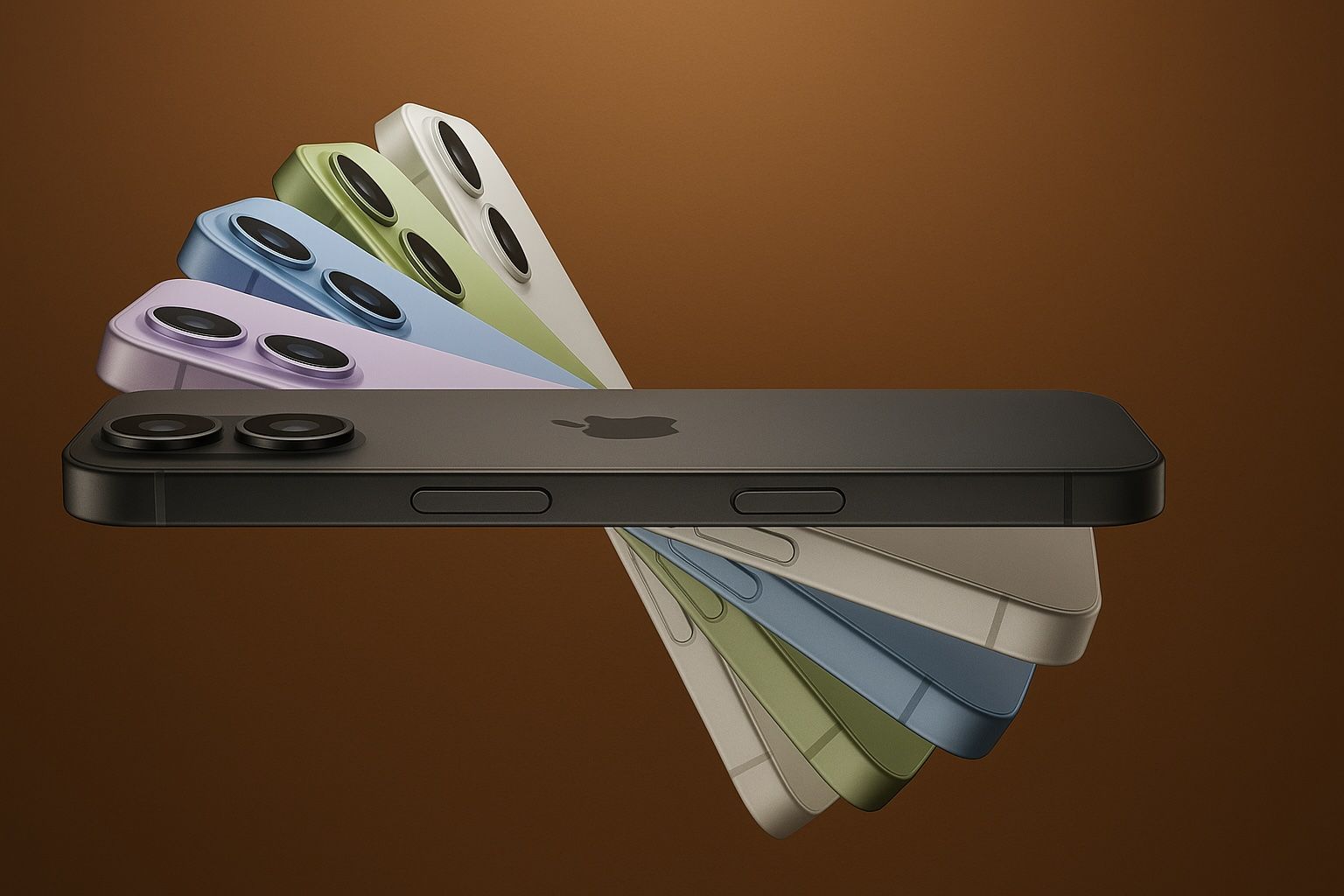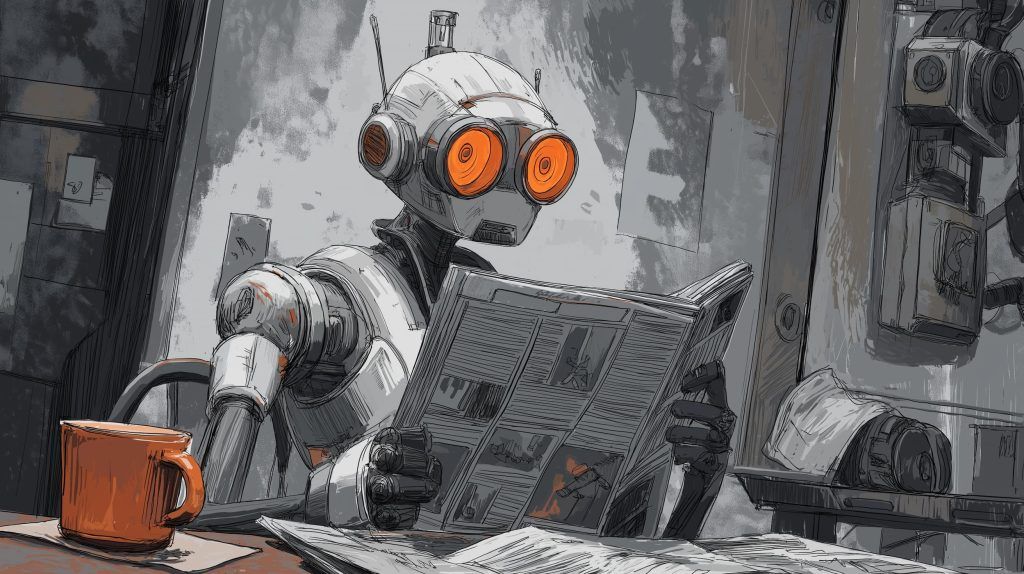- 三機種は共通して26.1MPのX-Trans CMOS 4センサーとX-Processor 4を搭載し、2020年〜2021年発売のミッドレンジ機として旗艦級の画質を手頃な価格で提供します。
- X-S10だけが5軸のボディ内手ブレ補正(最大約6段分)を搭載しており、X-T30 IIとX-E4にはIBISがありません。
- X-S10はマグネシウム前面プレートをヒートシンクとして4K動画を最大30分まで記録可能ですが、X-T30 IIとX-E4は約10〜20分程度に抑えられます。
- 3機種はDCI/UHD 4K@30pと1080p@最大240pの動画記録に対応し、内部は8bit 4:2:0、外部出力で10bit 4:2:2のF-Logにも対応します(機種によりファームウェア状況が異なることがあります)。
- オートフォーカスは全機種がハイブリッドAFを搭載し、顔・瞳検出や被写体追尾を備え、X-T30 IIは-7EV、X-E4も-7EV、X-S10は-6EV程度の低照度性能の差があります。
- EVFは0.39型236万ドット、約0.62倍、視野率100%で共通し、X-E4のEVFは左配置、X-T30 II/X-S10は中央配置、背面液晶はX-T30 IIが3.0型162万ドット、X-E4が3.0型162万ドットで180°チルト、X-S10は3.0型104万ドットのフル可動液晶です。
- デザイン面ではX-T30 IIがクラシックな一眼レフ風、X-E4がレンジファインダースタイルのミニマリズム、X-S10が現代的な一眼レフスタイルで、重量はX-T30 IIが383g、X-S10が約465g、X-E4は軽量設計です。
- レンズ互換性は全機種がXマウントで、XF/XCレンズとの組み合わせが可能で、X-S10は大口径レンズも快適、X-E4はパンケーキなど小型レンズが相性良いとされています。
- ファームウェアはX-T30 IIが2024年3月にv2.04、X-E4は生産終了、X-S10は2021年6月にv2.00以降v3.00/v3.10で機能改善、2025年時点で新機種の噂もあり、継続的なアップデートは限定的です。
- 現在の価格・流通は2025年8月時点で、X-T30 II新品は入手困難で米800–900ドル、X-E4新品はほぼなし中古700–900ドル、X-S10新品は在庫僅少で中古600–700ドル程度です。
Fujifilm X-T30 II、X-E4、X-S10は、いずれもFujifilmの定評ある26.1MP X-Trans CMOS 4 APS-CセンサーとX-Processor 4エンジンを搭載した、密接に関連するミラーレスカメラです。2020~2021年に発売され、これらのモデルはフラッグシップレベルの画質を、より手頃な価格で提供します。2025年現在も、より新しいモデルが登場している中で、愛好家や新進気鋭の写真家に人気の選択肢となっています。この包括的な比較では、技術仕様、写真および動画性能、オートフォーカスと連写、デザインと操作性などを詳しく検証します。また、現在の価格や入手状況、Fujifilmの今後の展開(X-T50、X100VI、X-Pro4の最新情報を含む)についても解説します。
詳細な比較に入る前に、まずはスペックの概要を簡単にご覧ください。
概要:主な仕様
| カメラ | センサー&プロセッサー | 手ブレ補正 | EVF | 液晶画面 | 連写 | 動画最大 | 重量(バッテリー込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm X-T30 II | 26.1MP X-Trans CMOS 4 X-Processor 4 | IBISなし(レンズOISのみ) | 0.39型 236万ドット OLED 0.62倍ファインダー倍率 | 3.0型 チルト式TFT 162万ドット | 最大8コマ/秒(メカシャッター)、電子シャッター時最大30コマ/秒(1.25倍クロップ) | DCI/UHD 4K @30p 1080p 最大240p | 383g |
| Fujifilm X-E4 | 26.1MP X-Trans CMOS 4 X-Processor 4 | IBISなし(レンズOISのみ) | 0.39型 236万ドット OLED 0.62倍ファインダー倍率 | 3.0型 チルト式TFT 162万ドット(180°フリップアップ) [1] | 最大8コマ/秒(メカシャッター)、電子シャッター時最大30コマ/秒(1.25倍クロップ) | DCI/UHD 4K @30p 1080p 最大240p | 364g |
| Fujifilm X-S10 | 26.1MP X-Trans CMOS 4 X-Processor 4 | 5軸IBIS(最大約6段分) | 0.39型 236万ドット OLED 0.62倍ファインダー倍率 | 3.0型 バリアングルTFT 104万ドット | 最大8コマ/秒(メカシャッター)、電子シャッター時最大30コマ/秒(1.25倍クロップ) | DCI/UHD 4K @30p 1080p 最大240p [2] | 465g [3] |
X-E4はX-T30 IIと同じ連写仕様(メカシャッター8コマ/秒、電子シャッター全画素20コマ/秒、電子シャッター1.25倍クロップ時30コマ/秒)です。
表から分かる通り、3機種ともに基本的な画質は同じで、Fujifilmの26MP BSI X-Trans 4センサーとクアッドコアプロセッサーを搭載しています。違いはボディ形状や機能、操作性にあります。これらの違いを分かりやすく解説し、どのモデルがあなたに最適かを見ていきましょう。
画質とセンサー性能
センサーとプロセッサー: 各カメラは富士フイルムの第4世代APS-CセンサーとX-Processor 4エンジンを搭載しており、X-T30 II、X-E4、X-S10の間で基本的な画質はほぼ同一です。3機種とも14ビットRAW(RAF)撮影が可能で、富士の人気フィルムシミュレーションによる優れたJPEGを生成します。実際、イメージングパイプラインは上位機種のX-T4と同じであり、「フラッグシップモデルと同じ優れた画質」が期待できます。ダイナミックレンジや高ISOノイズ性能も、その時代の最高のAPS-Cカメラと同等です。つまり、どちらを選んでも画質を犠牲にすることはありません ― 違いは他の部分にあります。
各カメラのネイティブISO範囲は160~12,800(拡張で80~51,200)で、富士のフィルムシミュレーションモードを共有しています(X-T30 IIはClassic Neg.やEterna Bleach Bypassなど新しいものを含む18種類のフィルムシミュレーションで発売)。すべて14ビットRAWや16ビットTIFF出力に対応し、ポストプロセスの自由度が最大限に広がります。X-T30 IIは2021年のリフレッシュモデルのため、オリジナルのX-T30よりいくつかのフィルムシミュレーションと改良されたAUTOモードが追加されており、X-E4やX-S10も同時期発売のため同じ機能を持っています。
実際には、3機種とも富士らしい色再現で美しい写真を生み出します。カメラから出てくるJPEGの色も素晴らしく、例えばDPReviewは「X-E4のデフォルトJPEGカラーは…魅力的に見える」とし、黄色、緑、青が正確に再現されていると評価しています。富士フイルムのフィルムプロファイル(Velvia、Acros、Classic Chromeなど)は多くのユーザーにとって大きな魅力で、3機種すべてで利用可能です。
独自のセンサー実装: 同じセンサーを搭載しているものの、実装には細かな違いがあります。X-T30 IIとX-E4にはボディ内手ブレ補正がありません。そのためボディはコンパクトですが、暗所ではレンズの光学式手ブレ補正や三脚に頼る必要があります。X-S10は5軸ボディ内手ブレ補正(IBIS)を搭載しており、X-H1/X-T4由来の「小型化された」IBISユニットを採用しています。これにより、X-S10は低速シャッターや動画撮影時の手持ち撮影で大きなアドバンテージがあります ― 詳細は下記のIBISセクションで解説します。
もう一つの違いは動画の熱管理です。X-S10はやや大きめのボディとマグネシウム合金製フロントプレートがヒートシンクの役割を果たし、4K録画を最大30分間可能 [4]。一方、より小型のX-T30 IIやX-E4は、サイズの都合で4K録画の安全な時間が短く(10~20分程度)、オーバーヒートやファイルクリップ制限に達しやすいです。次に動画仕様について詳しく見ていきます。
動画機能とパフォーマンス
レンジファインダーや一眼レフ風の外観にもかかわらず、3機種とも優れた動画カメラとしても活躍できます ― ただし富士の動画特化モデルと比べると制限もあります。全機種でセンサー全幅からのオーバーサンプリング4Kやスローモーション1080p撮影が可能で、カジュアルな動画用途にも対応できる多用途なハイブリッド機です。
- 解像度とフレームレート: 各カメラはDCI 4K(4096×2160)およびUHD 4K(3840×2160)を最大30pのフレームレートで記録できます。フルHD(1080p)では、最大240fpsで10倍スローモーション撮影が可能です。この1080/240pのハイスピードモードはX-E4およびX-T30 IIのリフレッシュで導入され、オリジナルのX-T30にはなかった超スローモーション機能を実現しています。
- 10ビットとF-Log: 内部記録では8ビット4:2:0(H.264コーデック、最大約200Mbps)で動画を記録します。しかし、3機種とも富士フイルムのF-Logフラットプロファイルを搭載し、外部記録用にmicro-HDMIポート経由で10ビット4:2:2動画を出力できます。例えば、10ビットHDMIをAtomosレコーダーに記録しつつ、同時にF-Logを内部(8ビット)で記録することも可能です。X-S10とX-T30 IIはファームウェアアップデート後に新しいF-LogおよびF-Log2プロファイルにも対応し、ダイナミックレンジが拡大され高度なカラーグレーディングが可能になります(正確な対応状況はモデルやファームウェアによって異なります)。
- 録画制限: 先述の通り、X-S10は効率的な放熱設計により1クリップあたり約30分の4K録画が可能です [5]。X-T30 IIとX-E4はよりコンパクトなため、通常4Kクリップ長は約10分(X-T30からの制限を引き継ぎ)です。これにより、X-S10は長時間の撮影(インタビューやイベント撮影など)により適しており、X-E4/T30IIは短いクリップやBロールに最適です。全モデルで1080pは最大30分まで録画可能です。
- 動画用IBIS:X-S10のIBISは動画撮影において大きな変化をもたらします。X-S10の手持ち撮影は、歩行時やパン時でも、非搭載のX-E4やX-T30 II(同等の滑らかさを得るには手ブレ補正レンズやジンバルが必要)と比べてはるかに滑らかです。実際、PetaPixelのレビューでは「富士フイルム機で体験した中で最高のIBIS性能」とX-S10の手ブレ補正が高く評価されました。X-S10にはさらにデジタルジンバルモード(ソフトウェアIS)も搭載され、必要に応じてさらなる安定化が可能です。
- オーディオと端子: 3機種とも3.5mmマイク入力端子を備えています。X-S10はさらに3.5mmヘッドホンジャック(同梱のUSB-Cアダプター経由)で音声モニタリングが可能ですが、X-T30 IIとX-E4には内蔵ヘッドホン出力がありません(USB-Cやホットシューアダプターを利用する必要があり、利便性は劣ります)。全モデルで映像出力用にmicro-HDMI端子、データ転送・充電用にUSB-Cを採用しています。
まとめると、3機種とも富士らしい美しい色味でシャープかつ高精細な4K動画を撮影できますが、本格的な動画撮影にはX-S10が明らかに最適です。IBIS、長時間録画、ヘッドホンモニタリングの組み合わせにより、より万能な動画ツールとなっています。X-E4とX-T30 IIも高品質な映像を十分に撮影でき(カジュアル用途では「十分に強力な動画性能」)、三脚固定や静止撮影には最適ですが、安定化機材なしでの長回しや動きのある撮影には向きません。
オートフォーカス性能と連写撮影
すべてのカメラは、フジのハイブリッドオートフォーカスシステムを搭載しており、撮像素子上の位相差検出がフレームのほぼ100%(216万位相差画素)をカバーしています。シングルショットAFでは、最大425点の選択可能なAFポイント(または簡易的な117点グリッド)を利用できます。顔・瞳検出、被写体追尾、ゾーンAFモードも搭載しています。ただし、これらのモデル間でAFの段階的な改良が見られます:- AF速度&アルゴリズム: X-T30 IIは、初代X-T30と比べてアップデートされたAFアルゴリズムで登場し、特に低照度や動体追尾での性能が向上しています。フジフイルムは、0.02秒の合焦速度と、前モデルよりも優れた顔・瞳検出を謳っています。実際、X-T30 IIはf/1.0レンズ装着時に暗所で-7EVまでオートフォーカスが可能で、旧X-T30の約-3EVより大幅に向上しています。2021年初頭に発売されたX-E4も同世代のアップデートにより、同様に-7EV付近までの合焦を誇ります。X-S10(2020年末発売)はX-T4に近いAF性能で、ほとんどの状況で優秀ですが、極端な低照度ではやや感度が劣り(約-6EV)、他2機種よりわずかに劣ります。実際には、いずれの機種も良好な光の下では素早く確実に合焦し、明るいレンズを使えば暗所でも十分対応できます。
- 顔・瞳検出: すべてのモデルが顔・瞳検出AFを搭載しており、ポートレートやスナップ、Vlog撮影に最適です。シーン内の顔を自動で検出・追尾します。ファームウェアアップデートにより、フジフイルムは瞳AFの信頼性も向上させています。ただし、動体追尾はこれら中級フジ機の弱点であり、他社にやや遅れを取っています。DPReviewによれば、AF追尾性能はソニーなどのライバル機に比べて劣るとのこと。スポーツや野生動物など高速な動きの被写体では、最新の他社AFシステムに比べて追従が難しい場合があります。シングルショットやゆっくり動く被写体なら問題ありません。
- ユーザーコントロール: X-E4にはAFモードセレクタースイッチがない点が異なります。従来のX-Eシリーズとは異なり、フジは本体からM/C/Sフォーカスモードの専用トグルスイッチを省略し、よりシンプルなデザインにしています [6]。メニューやファンクションボタンでシングル・コンティニュアス・マニュアルフォーカスを切り替えられますが、X-E4では操作性がやや妥協されています。X-T30 IIとX-S10にも物理的なフォーカスモードスイッチはありません(X-T30 IIの前モデルには前面にスイッチがありました)。代わりにクイックメニューやボタン割り当てでAFモードを切り替えます。これは、上位機種のフジカメラが素早いAFモード切替用スイッチを備えているのとは異なります。
連写性能: コンパクトなボディながら、これらのカメラは驚くほど高速な連写が可能です:
- いずれもメカニカルシャッターで最大8コマ/秒(フル解像度)で撮影できます。子供やペット、中程度のアクション撮影には十分な速度です。電子シャッターモード(無音撮影)では、フル解像度で最大20コマ/秒、または1.25倍クロップで30コマ/秒(センサーが約1600万画素にクロップされて30コマ/秒を実現)で撮影可能です。これらの速度は、上位機種X-T3/X-T4にも匹敵します。
- バッファおよび連写枚数(バースト深度): フラッグシップモデルと異なる点は、バッファ容量です。X-T30 IIやその兄弟機は内蔵メモリが小さいため、例えばX-T5のように8コマ/秒のRAW連写を長時間続けることはできません。富士フイルムの仕様によると、X-T30 IIは20コマ/秒でRAW(ロスレス圧縮)約17枚、またはJPEG約32枚をバッファがいっぱいになるまで撮影できます。PetaPixelのX-S10のテストでは、バッファがいっぱいになるまで30コマ/秒(クロップ時)でRAW約11枚と記録されています [7]。実際のところ、RAWでの高速連写は約1~2秒分しか撮影できません。JPEGのみなら、もう少し長く(20コマ/秒で約3秒分)撮影できます。X-S10とX-T30 IIは、以前のモデルよりわずかにバッファが改善されています。例えば、X-T30 IIのバッファは8コマ/秒でRAW約17枚、X-S10は18枚(大きな差ではありません)です。いずれもUHS-I SDカードを使用するため、書き込み速度は非常に速いわけではありません。連写を多用する場合は、高速なUHS-Iカードと、バッファがクリアされるまでの待ち時間に多少の忍耐が必要です(X-E4/X-T30IIは連写後、完全にバッファがクリアされるまで約8~10秒かかります)。
まとめると、日常の撮影や適度なアクション撮影には、これらのカメラのAFと連写性能で十分対応できます。顔やペット、スナップのピント合わせも得意で、短い連写で決定的瞬間を捉えられます。ただし、本格的なスポーツやアクション撮影で、8~15コマ/秒の連写を長時間続けたり、完璧なトラッキング性能が必要な場合は、これらのボディでは物足りなくなるかもしれません――「最高のAF性能を求めるスポーツ・アクション撮影者」にとっては、トラッキング性能が制限となる可能性があります。富士フイルムの上位機種X-H2Sや、ソニーa6x00シリーズなどの競合機種の方が、その分野では優れています。それ以外の用途なら、十分に活躍してくれるでしょう。
ボディデザイン、操作性とコントロール
これらのモデル間で最も大きな違いの一つは、ボディデザインとエルゴノミクス(操作性)です。富士フイルムは、それぞれ異なるスタイルで展開し、さまざまな好みに応えるようにしています:
- X-T30 II:レトロなダイヤルを備えた一眼レフスタイル – X-T30 IIは、クラシックな富士フイルムの一眼レフ風デザイン(ミニX-T3/X-T4)で、電子ビューファインダーがペンタプリズムの出っ張りのように中央に配置されています。上部には伝統的なダイヤルがあり、シャッタースピードダイヤル、露出補正ダイヤル、静止画/動画用のモード切替スイッチを備えています。専用のISOダイヤルはなく(ISOはボタンやオートISO設定で調整します。ISOダイヤルは上位のX-Tモデルのみ搭載)、X-T30 IIのダイヤル操作は、手触りやアナログ感を好む人にとっては魅力的です。「X-T30 IIのすべての要素は写真家のために設計されており…最先端の機能とヴィンテージな美的魅力を融合しています」と富士フイルムは述べています [8] [9]。さらに、上部ハウジングに隠れた内蔵ポップアップフラッシュも搭載しており、補助光が必要なときに便利です。X-T30 IIのボディはコンパクトかつ軽量(383g)で、控えめなフロントグリップとサムレストを備えています。外観は初代X-T30と非常によく似ており、実際、デザインや操作系はまったく同じです(カメラ前面のネームバッジも「X-T30」と表記されたまま)。唯一の外観上の違いは、底面プレートの小さなラベルです。Mark IIでは背面液晶が高解像度パネル(162万ドット、従来は104万ドット)にアップグレードされましたが、チルト式のままです(上方向90°、下方向約45°)。ウエストレベルや頭上からの撮影に便利ですが、前方には反転できませんので自撮りやVlogには不向きです。
- X-E4:レンジファインダースタイルのミニマリズム – X-E4は、ビューファインダーが左端にあるレンジファインダースタイルの小型でフラットなボディのカメラです。ミニマルなデザインの理念を採用しています。富士フイルムは、前モデルにあったいくつかのボタンや背面グリップさえも取り除き、非常にクリーンな外観(ただしダイレクトコントロールも減少)を実現しました [10]。上部にはシャッタースピードダイヤル(「P」プログラムモード設定を含む)と露出補正ダイヤルがあります。特筆すべきは、X-E4には内蔵フラッシュがないことです(旧型のX-E3とは異なります)。代わりに、初期出荷分には小型のシュー装着型フラッシュが同梱されており、必要に応じて外部フラッシュも使用できます。X-E4の背面にはDパッドの方向ボタンはなく、ジョイスティックといくつかのフラットなボタンのみです。X-E3と比べてAFモードセレクタースイッチやリアコマンドダイヤルも廃止されています [11] [12]。その結果、ポケットに入るほどスリムなカメラとなりました(特に幅と奥行き-厚さはわずか33mm)。3.0型チルト式液晶は180°反転して前面を向くことができ、X-Eシリーズ初の機能です [13]。これは自撮りやVlogに最適ですが、反転時はトッププレート上に液晶が位置するため、ホットシューに何か装着していると遮られる可能性があります。X-E4のEVFはわずかに突き出しているだけで、グリップがないことと相まって、パンケーキレンズ装着時はほぼコートのポケットにも収まります。多くのユーザーがX-E4の純粋さとスタイルを愛しており、「優れた画質を実現するスタイリッシュなカメラ…ブランド最小のXマウント機で、ストリート、旅行、汎用フォトグラファーに最適」と評されています。しかし、ミニマリズムは諸刃の剣でもあり、「富士は少しミニマルにしすぎた」と感じる写真家もおり、ボタンが限られているため設定への素早いアクセスやカスタマイズに時間がかかることもあります。幸い、X-E4ではタッチスクリーンスワイプジェスチャーで4つの仮想ファンクション「ボタン」を割り当てることができます。エルゴノミクス的にはX-E4は非常にフラットで滑りやすく感じることがあり、富士は追加のハンドグリップやサムレストを販売しており、多くのユーザーが快適な操作のために必須と考えています。ビルド面では、マグネシウム製トッププレートと魅力的なフェイクレザー巻きでしっかりした質感ですが、防塵防滴ではない点には注意が必要です(この3機種すべてに共通)。
- X-S10:現代的な操作系を備えた一眼レフスタイル – X-S10は、富士フイルムの従来のレトロな操作系とは異なるアプローチを取りました。現代的な小型一眼レフのようなスタイルで、上部には専用のシャッター/ISOダイヤルの代わりに、深いグリップと一般的なPASMモードダイヤルを備えています。富士フイルムは、従来のダイヤル方式に馴染みのない(特にキヤノンやニコンの一眼レフから来た)初心者層にアピールするため、X-S10を明確に設計しました。PetaPixelが指摘したように、「PSAMダイヤルのレイアウトは熱心な富士フイルムユーザーから批判されるかもしれないが、富士フイルムが[X-S10]をシンプルさ重視で設計しているのは明らかであり、それが新規ユーザーをシステムに引きつける可能性がある」とのことです。X-S10の上部プレートには、モードダイヤル(オートやカスタムポジションあり)、コマンドダイヤル、目立つ動画記録ボタンがあります。さらにユニークなのは、左肩にフィルムシミュレーションダイヤルがあることです。デフォルトでは、富士フイルムのフィルムルックをプレビュー・選択できるクイックメニューが表示され、説明も付いており、システムを学ぶ人にとって楽しい工夫です。X-S10のグリップは素晴らしく、「小型カメラとしてはエルゴノミクスが非常に優れており…とても快適に使える」と評されています。X-S10は、X-T30 IIやX-E4では前が重く感じるような大きめのレンズとも相性が良いです。また、X-S10は完全に可動するバリアングル3型液晶を搭載し、横に開いて180°回転できるため、Vlog撮影や変則的なアングルでの撮影に最適です。この3機種の中で唯一のフリップアウト式液晶(他はチルト式のみ)です。ビルド面では、X-S10はIBISユニットとグリップのためやや大きく重く(バッテリー込みで約465g)なっていますが、本格的な一眼レフと比べれば依然コンパクトです。他の2機種同様、防塵防滴仕様ではありません。X-S10には小型のポップアップフラッシュがファインダー部に内蔵されています(X-T30 IIと同様) [14]。全体として、X-S10はまったく異なる操作感を持ち、現代的な使いやすさを優先して一部のアナログ的な魅力を犠牲にしています。「どんな写真家でもこのシステムにはすぐに慣れるだろう」とPetaPixelは述べており、ほぼすべてのボタンがカスタマイズ可能で、レイアウトも馴染みやすいです。
まとめると、操作性の違いは主に好みの問題です。レトロなデザインやダイレクトダイヤルが好きなら、X-T30 IIが小型ボディでそれを実現します。さらに小型で、ミニマルなレンジファインダースタイルが気にならない(または好む)なら、X-E4は富士フイルムのラインナップでもユニークな存在です – 「X-E4はスタイリッシュで軽量なカメラ…旅行やスナップに最適な相棒」ですが、操作性に妥協点もあり(多くのX-E4ユーザーは快適性向上のためグリップやサムレストを追加しています)。快適さや大きなグリップ、シンプルな操作性を重視するなら、X-S10が魅力的かもしれません – 「X-S10は非常にコンパクトでありながらエルゴノミクスが優れている…過剰な作りではなく、とても快適に使える」。
なお、これらのボディはいずれも防塵防滴仕様ではありません。このクラスとしてはしっかりした作り(X-T30IIとX-E4は金属製トップ/ボトムプレート、X-S10はマグネシウム合金シャーシ)ですが、防塵・防滴が必要な場合はX-T5やX-Proシリーズなど上位モデルを検討する必要があります。
ファインダーとディスプレイ
3機種とも、同様の電子ビューファインダー(EVF)を搭載し、背面液晶はそれぞれ異なる可動方式となっています:
- ビューファインダー: いずれも0.39インチOLED EVFを搭載し、236万ドットの解像度と約100%の視野率を持ちます。倍率は約0.62倍(35mm換算)で、これは十分ですが、上位モデルと比べるとやや小さめです。実際には、EVFはほとんどの用途で十分明るく詳細ですが、より大きなファインダーから移行したユーザーにはやや窮屈に感じるかもしれません。3機種とも、ブーストパフォーマンスモードで最大100Hzのリフレッシュレートに対応しており、ライブビューは非常になめらかで遅延も最小限です。物理的な違いも少しあり、X-E4のEVFアイピースは左側に配置されています(レンジファインダー愛用者には好まれ、左目でファインダーを覗きながら右目で周囲を確認できます)。X-T30 IIとX-S10はEVFが中央にあります。眼鏡使用者からは、0.62倍の倍率は眼鏡でも使えるが、特別大きいわけではないと指摘されています。同じスペックでも、体験は異なる場合があります。X-E4のファインダーはX-T30 IIと本質的に同一(同スペック)ですが、左端の配置により、鼻が背面液晶に当たらないという利点があります。ただし、X-E4の小型ボディでは、顔が特定のボタンを押そうとした際にアイセンサーを誤作動させることがあり(DPReviewによると、親指がEVFアイセンサーに触れてLCDが意図せず消えることがある)、 [15]。X-S10のEVFも2.36Mドット/0.62倍で、グリップが大きいため目に当てやすく、アイセンサーによる自動切り替えも搭載しています。これらのEVFはいずれもX-T4(369万ドット、0.75倍)やX-T5(0.8倍)の大型・高解像度ファインダーには及びませんが、エントリー~ミドルクラス機としては競合機と同等です。X-T30 IIとX-E4のEVFは「標準的…傑出はしないが十分」と評されています [16]。マニュアルフォーカス時も、ピーキングやデジタルスプリットイメージ補助で快適に使えます。
- 背面液晶: ここでは3つのアプローチがあります:
- X-T30 IIは、2軸チルト式3.0インチ液晶を採用(上約90°、下約45°までチルト)。特筆すべきは、X-T30 IIの画面解像度が162万ドットにアップグレードされた点(初代X-T30は104万ドット)。これにより画像確認がより鮮明になりました。また、タッチスクリーンで、タッチフォーカス、スワイプ操作、メニュー操作に対応。チルト式はローアングルのストリート撮影やウエストレベル撮影に最適ですが、前方には向かないため、X-T30 IIは自撮りやセルフ動画には不向きです。画面は横方向には可動しないため、カメラがスリムに保たれ、静止画派には好まれる設計です。
- X-E4は独自のチルト式LCDを搭載しています。ウエストレベル撮影用に90°上方向にチルトし、さらに自撮り用に前面に向けて180°上方向に反転できます [17]。反転時にはライブビューがミラー表示され(情報表示も自動で正しい向きに反転します) [18]。これは、サイドヒンジなしで前面撮影を可能にする巧妙な解決策です。X-E4の画面は3.0型 162万ドット タッチスクリーン [19]で、基本的にX-T30 IIと同じパネルです。閉じたときは背面とフラットになり、カメラのスリムな外観に貢献しています。注意点として、ホットシューに外部マイクやフラッシュなどを装着していると、画面が完全に反転できない場合があります。それ以外は、時々Vlogや自撮りをしたい人には最適です。突出したヒンジのないフラッシュデザインは非常にエレガントです。
- X-S10はフルアーティキュレーティング・バリアングル3.0型タッチスクリーン(104万ドット)を採用しています。側面にスイングアウトし、180°前方に回転でき、内側に折りたたんで画面を保護することも可能です。これは動画クリエイターにとって最も多用途で、どんな角度(ロー、ハイ、前面)にも調整できます。一部の静止画撮影者はサイドヒンジ式画面を好まない場合もあります(ウエストレベルで縦位置撮影する場合、チルト式の方が素早いことも)、しかし柔軟性は否定できません。解像度(104万ドット)は他の2機種の162万ドットよりやや低いですが、実用上は十分です。X-S10のタッチインターフェースは反応が良く、EVFを覗きながらでも(画面上で親指を使ってフォーカスポイントを移動するなど)使用できます。
いずれの場合も、タッチスクリーン機能により、タップでフォーカスしたり、再生時に画像をスワイプして閲覧できます。X-E4は物理ボタンが少ないため、特にタッチスクリーンの恩恵を受けており、富士は4つのカスタム「スワイプ」ジェスチャーを設定でき、事実上バーチャルファンクションボタンを追加できます。
勝者は?自撮りやVlog用画面を重視するなら、X-S10またはX-E4がX-T30 IIより優れています。純粋に伝統的な静止画用途では、X-T30 IIやX-E4のようなチルト式(サイドヒンジなし)のシンプルさを好む人もいます。X-T30 II/X-E4のLCDの高解像度(162万ドット)は、厳密なピントチェックに便利です。しかし、X-S10のフルアーティキュレーティング画面が全体的に最も多用途で、特に動画用のIBISと組み合わせると優れています。なお、これらのカメラはいずれもX-T3のような巧妙な3方向チルトには対応していませんが、基本はカバーしています。
ボディ内手ブレ補正(IBIS)と撮影安定性
主な機能面での違いのひとつは、ボディ内手ブレ補正の有無です。
- Fujifilm X-S10: 5軸手ブレ補正(IBIS)を内蔵。これは発売当初の目玉機能で、X-S10はミドルレンジの富士フイルム機として初めて手ブレ補正を搭載し、X-T4由来の新型小型IBISユニットを採用しています。最大5~6段分の手ブレ補正効果を発揮します(公式には特定レンズで約6段、他のレンズではやや少なめ)。実際には、手持ちで1/8秒や1/4秒のシャッタースピードでも十分撮影可能で、1秒程度の露光も安定した手持ちなら成功することもあります。動画撮影ではIBISは非常に価値があり、手持ち映像を大幅に滑らかにします。PetaPixelは、「X-S10には[IBISが]あり、富士フイルム機で体験した中で最高のパフォーマンスだ」と当時評しており、静止画・動画の両方で優れた効果を発揮すると述べています。X-S10のIBISは、光学式手ブレ補正(OIS)搭載レンズと連携してさらに高い効果を発揮します(レンズ+ボディのダブル補正)。OIS非搭載の単焦点レンズ(例:人気のXF 23mm f/2、35mm f/1.4など)でも、低照度や動画撮影で新たな使い勝手をもたらします。
- Fujifilm X-T30 IIとX-E4: IBIS非搭載です。これらのカメラは、従来通りレンズ側の手ブレ補正や高ISO/高速シャッターでブレを防ぐ必要があります。多くのXFズームレンズ(例:18-55mm、16-80mm、55-200mm)は光学式手ブレ補正を搭載しており、これらと組み合わせれば効果的です。OIS非搭載の単焦点レンズでは、ブレを防ぐためにシャッタースピードを上げる必要があります(APS-Cの場合、一般的に1/(焦点距離×1.5)秒以上、または三脚/一脚の使用推奨)。2600万画素APS-Cは多くの状況で十分許容範囲と言えますが、IBISがあれば手持ち撮影の幅が大きく広がるのは否定できず、動画撮影でも非常に有用です。
実際の使用感としては、暗所撮影が多い場合、X-S10なら手持ちでシャッタースピードを遅くできるため、ISOを低く抑えられます。例えば、X-S10+18mmレンズで1/5秒でもブレずに撮れることがあり、X-E4やT30IIではサポートなしではほぼ不可能です。同様に、OIS非搭載の望遠レンズ(富士のラインナップには少数ですが、ほとんどの望遠ズームはOIS搭載)を使う場合も、X-S10のIBISは非常に頼りになります。
主に日中やストリート撮影、長時間露光で三脚を使う場合は、IBISの重要性はそれほど高くないかもしれません。しかし、旅行写真(薄暗い教会や夕景)や動画撮影では、X-S10のIBISは決定的なアドバンテージとなります。富士フイルム自身も認めており、X-T30 IIやX-E4には手ブレ補正がなく、「このクラスでIBISが欲しければX-S10にステップアップを」と案内しています。
まとめると、IBIS搭載状況: X-S10 あり、X-T30 II なし、X-E4 なし。ただし、2025年時点で富士フイルムは新型X-E5(X-E4の後継)にIBISを搭載し、小型ボディでも手ブレ補正が可能になりました。 しかし、この3機種の中で手ブレ補正が使えるのはX-S10だけです。
レンズとマウント互換性
3機種ともFujifilm Xマウントを採用しており、富士フイルム純正のXF・XCレンズやサードパーティ製Xマウントレンズに完全対応しています。マウントに違いはなく、どのカメラでも同じレンズが使えます。
レンズ選びの際の注意点・おすすめ:
- バランスと操作性:X-E4とX-T30 IIは非常にコンパクトなボディで、同様に小型のレンズと組み合わせるのが最適です。これらは、XF 27mm f/2.8「パンケーキ」(X-E4は27mmとのキットも用意され、ジャケットのポケットにも入る組み合わせ)、XF 35mm f/2、23mm f/2、50mm f/2「フジクロン」シリーズ、または小型のXC 15-45mmパワーズームなど、富士フイルムのコンパクトな単焦点レンズと非常に相性が良いです。これらのレンズはセットアップを軽量かつバランス良く保ち、ストリートフォトや旅行に最適です。一方で、大きなレンズ(例えばXF 16-55mm f/2.8や50-140mm f/2.8)を装着すると、X-E4/T30IIでは前方が重く感じられ、特にX-E4はグリップがないため大きなレンズでは扱いが難しくなります。確かに使用は可能ですが(光学的には問題ありません)、エルゴノミクス的にはアクセサリーグリップを追加しないと理想的とは言えません。
- X-S10のグリップの利点: X-S10のしっかりしたグリップとIBIS(ボディ内手ブレ補正)により、レンズの選択肢が非常に広がります。大きなズームや望遠レンズもより快適に扱うことができます。例えば、XF 16-80mm f/4 OIS(富士の優れた汎用ズームの一つ)はX-S10のキットとしてよく販売されており、旅行に最適な安定した組み合わせを実現します。カメラのIBISは、OIS(レンズ内手ブレ補正)がない16mm f/1.4や56mm f/1.2のような単焦点レンズにも効果的で、低照度での使用を安定させます。重いレンズを使う予定がある場合や、単焦点レンズで動画撮影を多く行う場合は、X-S10ボディがより適したプラットフォームです。
- キットレンズ: 発売時、富士フイルムはX-T30 IIをXC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ(非常にコンパクトなパワーズームレンズ)または上位のXF 18-55mm f/2.8-4 OIS(光学的に優れたキットズーム)とのキットで提供していました。X-E4の公式キットはXF 27mm f/2.8 R WRパンケーキ単焦点レンズとの組み合わせで、素晴らしいスナップ用セットアップです。X-S10はボディ単体、またはXF 18-55mmやXF 16-80mm f/4 OIS WRズームとのセットで販売されることが多かったです。これらのレンズはすべて素晴らしいスタートポイントです。特に、富士フイルムの18-55mm f/2.8-4キットレンズは非常に高く評価されており、高速・高画質・手ブレ補正付きで、一般的なズームを求めるならどのカメラにも最適なパートナーです。
- サードパーティ製レンズ: 近年、Xマウント対応のサードパーティ製レンズのサポートが大きく拡大しています。Sigma(16mm、30mm、56mm f/1.4 DC DNトリオ)やTamron(例:17-70mm f/2.8 OIS)などのAF単焦点レンズが利用可能で、これらのボディで問題なく動作します。また、Samyang、Viltrox、Laowaなどから多くのマニュアルフォーカスレンズも登場しており、興味のある方には選択肢が豊富です。良いニュースは、すべてのXマウントレンズがこれらのカメラで共通して使えることです。なぜなら、同じマウントとAPS-Cセンサーサイズを共有しているため(クロップファクターの違いはありません)。マニュアルレンズを使う場合でも、EVF内のフォーカスアシスト(ピーキング、拡大表示)はどの機種でも同様に役立ちます。
- 用途別レンズ提案:ストリートフォトには、X-E4に小型単焦点レンズの組み合わせが魔法のようなコンボです。例えばXF 23mm f/2や27mmパンケーキは目立たず撮影できます。旅行・Vlogには、X-S10と広角ズーム(XF 10-24mmや新しいXF 18-120mm f/4パワーズームなど)の組み合わせが最適です。IBISとバリアングル液晶が動画撮影や手持ち撮影の汎用性を高めます。ポートレート撮影には、どの機種でもXF 50mm f/1.0や56mm f/1.2が活躍しますが、重いレンズはX-S10の方が扱いやすい点に注意してください。オールドレンズ愛好家(ビンテージレンズの装着)には、X-S10のIBISが古いレンズも手ブレ補正でき、また大きなグリップで重いマニュアルレンズもバランス良く扱えます。
まとめると、これらのカメラ間で「レンズ互換性」に違いはありません ― どのレンズが各カメラにしっくりくるかが重要です。X-E4はコンパクトな単焦点レンズと組み合わせることで、そのロープロファイルな魅力を最大限に発揮します。X-T30 IIは万能型で、単焦点も中型ズームも両方こなせます。そしてX-S10はどんなレンズでも快適に使えます ― 小さなパンケーキレンズから赤バッジのズームまで ― そのため、レンズコレクションが増えていく場合は最も汎用性が高いと言えるでしょう。Xマウントのエコシステムは充実しており、どのボディを選んでも、何十本ものレンズを楽しむことができます。
どれを選ぶべき?それぞれの理想的な使い方
これらのカメラはそれぞれ独自のニッチを切り開いています。ここでは、理想的な使用例やユーザープロフィールを挙げます。どれが他よりも適しているかの参考にしてください。
- 旅行・日常の持ち歩き用:X-E4は、究極のトラベルバディです。サイズと重量を最小限にしたい場合に最適。富士フイルムのXシリーズで最も小型の交換レンズ式カメラで、小さなバッグや大きめのジャケットのポケットにも簡単に収まります。旅行やハイキング、日常的な持ち歩きに最適です。27mmパンケーキや18mm f/2と組み合わせれば、コンパクトデジカメとほぼ同じ大きさで高画質なカメラになります。また、非常にスタイリッシュなカメラの一つでもあり、旅行中に目立たず使いたい場合にもぴったり(シルバーとブラックあり)。旅行のVlogや自撮りにはX-E4のフリップアップ式液晶が便利ですが、IBISがないため、手ブレ補正付きレンズや後処理で映像を安定させる必要があります。
- ストリート・都市スナップ:X-E4とX-T30 IIの両方がここでは優れていますが、その方法は異なります。X-E4のレンジファインダー型は、右目でファインダーを覗きつつ左目で周囲を観察したいストリートフォトグラファーに人気です。サイレント電子シャッターとチルト式液晶(ウエストレベルファインダーのようにも使える)で、非常に目立たず撮影できます。ミニマルな操作系はゾーンフォーカスや予測撮影スタイルを促します ― 「誤ってボタンを押すことが減った…まさに私が求めていたもの」と、X100FからX-E4に移行したユーザーは語っています。一方、X-T30 IIはダイヤルによる素早い設定変更が可能で、動きのあるストリートシーンでシャッタースピードや露出補正を即座に調整したい場合に有利です。どちらも小型で目立ちにくいので、ストリートには最適です。X-S10もストリート撮影は可能ですが、やや大きく一眼レフ的な外観なので、ステルス性は劣ります。ただし、重めのレンズ(例:90mm f/2で遠くからのスナップ)を使う場合はグリップが役立つかもしれません。
- Vlog・YouTube:X-S10は動画・Vlog用途で明らかに最適です。唯一IBIS(手持ち歩き撮影の安定化)と、撮影中に自分に向けられるバリアングル液晶を備えています。ヘッドホンモニタリング(アダプター経由)も可能で、音声チェックも安心。X-S10ならショットガンマイクを上に付け、液晶を横に開いてVlog撮影が可能 ― IBIS+OISレンズの組み合わせで動きも滑らかです。X-E4も簡単な定点Vlogなら対応可能:液晶が前を向き、動画時はデジタル手ブレ補正(DIS)やジンバルも使えますが、X-S10ほど便利・滑らかではありません。X-T30 IIは前向き液晶もIBISもないため、Vlogには不向き。常にカメラマンがいる場合を除き、理想的とは言えません。
- ポートレートと人物撮影: 3機種とも、26MPセンサーと富士フイルムの色彩・トーン表現(クラシッククロームやプロネガのフィルムシミュレーションは肌に最適)のおかげで、美しいポートレート画像を生み出せます。カジュアルなポートレート愛好家にとっては、選択の決め手はエルゴノミクスかもしれません。X-S10は大口径ポートレートレンズ(例:56mm f/1.2や50mm f/1.0)との相性が最も良く、IBIS(ボディ内手ブレ補正)により短い望遠域でも手ブレを抑えられます。X-T30 IIも素晴らしく、特に光学/機械式シャッターダイヤルで操作したい方には最適です。X-E4ももちろんポートレート撮影が可能で(必要に応じてホットシュー経由で内蔵フラッシュによる補助光も使用可能)、ただし大きなレンズを使う場合やスタジオ撮影ではやや扱いにくいかもしれません。それでも、環境ポートレートやストリートポートレートには、X-E4と35mm f/2や50mm f/2の組み合わせは、被写体に威圧感を与えない軽快なセットアップとなります。
- スポーツ、アクション、野生動物: これら3機種の得意分野ではありませんが、もし選ぶなら—X-S10のグリップの良さと大きなバッファが望遠撮影でわずかに有利です。実際、素早い動きの被写体には、富士フイルムのX-T4やX-H2Sなど、より高度なAFと大容量バッファを持つ機種が理想的です。DPReviewも、「最高のオートフォーカスを求めるスポーツやアクションの専門家は…他を検討した方が良い」と結論付けています。ただし、カジュアルなスポーツ(子供の試合など)なら、バーストのタイミングを合わせれば十分対応可能です。X-S10とXF100-400mm(手ブレ補正付きレンズ)の組み合わせなら、IBIS+OISの効果で野生動物や航空ショーの撮影もこなせます。ただし、素早い被写体の最先端トラッキング性能は期待しないでください。
- 初心者と学生:X-T30 IIは、初心者に最適なカメラの一つとしてよく推奨されています。手応えのあるダイヤル操作で基本(シャッター、絞り、ISO)を学べるマニュアル操作体験が得られますが、トップのAutoスイッチ(オートモードレバー)で、素早くスナップしたい時は自動化も可能です。Digital Camera Worldは「初心者が求めるすべてが詰まっている」と評し、従来のエントリー一眼レフよりもシンプルで、富士フイルムのフィルムシミュレーションやレトロな外観の恩恵もあると指摘しています。X-S10も同様に初心者向け(むしろPSAMダイヤルでより親しみやすいかもしれません)で、「Auto/SP」モードによるシーン認識も搭載。スマートフォンからカメラに移行する初心者には、X-S10のシンプルなインターフェースが好まれるかもしれません。X-E4は最もシンプルな構成なので、ある意味初心者にも扱いやすいですが(ボタンが少なく混乱しにくい)、頻繁に設定を変えたい人にはメニュー操作が多くなり、やや不便かもしれません。写真コースの学生には、X-T30 IIが理想的かもしれません。クラシックなダイヤルで露出を学べ、プロジェクトにも十分対応できる性能を、手頃な価格で備えています。
- 日常の家族や旅行の動画・写真: もしオールラウンドなファミリーカメラを探しているなら、X-S10はあらゆることができる点で際立っています。DPReviewが言うように「優れた万能型フォトグラファー向けカメラ」です。子どもを撮るのにも最適(グリップがあるので、子どもを抱えながら片手で撮影しやすい!)、IBISは室内の低照度でも役立ち、動画もホームムービーに十分です。X-T30 IIもこの用途に使えます。特に、より小型なボディを好み、高度な動画機能が不要な場合におすすめです。多くの家族ユーザーが、旅行や日常生活用にX-T30シリーズを愛用しています。スマートフォンをはるかに超える画質を、コンパクトなボディで得られます。ただし、バッテリー寿命が短め(CIPA基準で約325~380枚、通常は1日分のカジュアルな撮影に相当)なので注意。予備バッテリーやUSBモバイルバッテリーを持ち歩き、必要に応じて充電しましょう(すべてUSB充電対応)。
- プロのバックアップやサブカメラ: これらのカメラは、富士フイルムを使うプロのバックアップボディとしても活躍します。例えば、X-T4やX-H2Sを使うウェディングフォトグラファーが、X-T30 IIやX-S10を軽量なサブ機として使うケースです。同じセンサーなので画質も揃います。制限点は、カードスロットが1つ(プロは即時バックアップのためデュアルスロットを好む)であることと、防塵防滴でないこと。重要な仕事ではリスクがありますが、実際にX-T30やX-E3をプロの現場で使っている人も多いです。3機種の中では、X-S10がプロのバックアップとして最適かもしれません。操作系は異なりますが、機能面(IBISなど)はフラッグシップに最も近いです。X-E4も十分使えますが、特に速い現場ではミニマルすぎるかもしれません。ステルス性が必要な場合は別です。
まとめ: とにかくコンパクトさとデザイン性を重視するならX-E4を選びましょう。単焦点レンズでのストリート・旅行・日常撮影に最適です。クラシックな富士の一眼レフスタイルとダイレクトダイヤルを小型ボディで楽しみたいならX-T30 II。写真の勉強や汎用的な用途にぴったりです。動画や多様なレンズを使いたい、より現代的な操作系でも気にならないならX-S10が最も万能です。 どれも同じように素晴らしい写真が撮れます。自分の撮影スタイルに合うデザインを選びましょう。あるレビュアーの言葉を借りれば、「X-E4はその小ささを本当に活かすなら最高…より万能な体験が欲しいならX-S10を選ぶべき」。
ファームウェア、機能、アップデート(2025年時点)
富士フイルムは、時に大きな機能追加を含むファームウェアアップデートでカメラをサポートすることで知られています。2020~2021年モデルであるこれらのカメラ、2025年時点でのアップデート状況は?
- X-T30 II: もともとマイナーチェンジモデルだったため、X-T30 IIには大きな機能追加のファームウェアはありません。X-T30よりも多くのフィルムシミュレーションや高解像度LCDなど、改良された機能セットで発売され、主にバグ修正のアップデートが行われています。2024年3月のファームウェアv2.04では、スマートフォンへの画像転送の不具合修正がありました。特に、テザー撮影はX-T30 II(およびX-T30)では非対応です。富士はこの機能を上位モデルに限定しているため、スタジオ撮影で必要な方は注意が必要です。カメラリモートアプリやWi-Fi/Bluetooth接続で、ワイヤレス画像転送やリモートシャッターは全機種で利用できます。
- X-E4: X-E4もマイナーなアップデートやバグ修正(例:稀なケースでの露出の不具合修正)を受けましたが、新しいフィルムシミュレーションや機能追加は発売時からありませんでした。2023年には多くの小売店で販売終了と表示されており(価格・流通の項で詳述)、安定性向上以外の大きなファームウェア変更は見られませんでした。X-E4は最後に登場したX-Trans IVセンサー搭載機(その後フジは新世代40MP機に移行)であり、FujiRumorsもこの機種がそのセンサー世代最後になると報じていましたが、2025年の後継機が出るまでその通りでした。
- X-S10: X-S10は、いくつか意味のあるファームウェアアップデートの恩恵を受けました。ファームウェア2.00(2021年6月)で、テザー撮影対応とジンバル制御(USB経由)が追加され、スタジオや映像制作者に最適です。また、FujifilmのWebカメラユーティリティ対応やAFアルゴリズムの改良も加わりました(こうしたAFの細かな改良は他機種にも波及することが多いです)。その後のアップデート(v3.00、v3.10)では絞り制御の最適化や軽微なバグ修正が行われました。2025年にはX-S20に後継され、フジの注力も移りましたが、X-S10は成熟したファームウェアで非常に完成度が高いです。もともと4:2:2 HDMI出力やF-Logなどの機能も備えていたため、不足はほとんどありませんでした。
全体として、これらのカメラはいずれもファームウェアで画期的な新機能が追加されたわけではなく、主に細かな改良にとどまっています。なお、フジは2023年に新しい接続アプリFuji X Appを導入し、ワイヤレス転送やリモート撮影体験の向上を図りました。これらのカメラもファームウェア更新後に新アプリが利用可能となり、QoL(使い勝手)の向上が見られます(旧Camera Remoteアプリは使いにくかった)。とはいえ、2025年時点でもX-E4、X-T30 II、X-S10はいずれも発売当初とほぼ同じ動作で、初期の不具合が解消された程度です。
小さな強化点として、X-T30 IIとX-S10はFuji GT-XproファイルトランスミッターをUSB経由でテザー撮影に利用できるようになりました(サードパーティ製品も存在)。ただし、プロ向けのニッチなワークフローツールを除けば、機能面は基本的に変わっていません。
まとめると、2025年時点でも機能面で大きな損はありません――これらのカメラは安定して洗練されています。ただし、より新しいフジ機(X-Processor 5搭載)は、これら旧機種では得られない機能(例:X-T5以降のNostalgic Neg.フィルムシミュレーション、被写体検出付きAF強化など)を備えています。とはいえ、価格やターゲット層を考えれば、これらの機種も十分に現役です。
現在の価格と流通状況(2025年8月時点)
2025年8月時点で、これらのモデルの状況はやや変化しています。主要市場での価格と流通状況について、購入希望者が知っておくべき点は以下の通りです:
- 富士フイルム X-T30 II: 2021年後半に$899 USD(ボディのみ)で発売され、2023~24年にはセールで$799程度で見かけることも多くなりました。しかし2025年には新品の入手が難しくなっています。後継機の発表により在庫が少なくなっており、例えば一部の小売店ではバックオーダーや在庫切れとなっています。入荷があれば、米国ではボディのみで$800~$900程度で推移しています。ヨーロッパではボディ新品が€849~899程度。イギリスでは発売時にボディのみで約£769(在庫があれば現在も£700~750程度)。レンズキットの場合は価格が異なります(例:18-55mm付きで元々約$1,299)。中古市場でもX-T30 IIは比較的高値を維持しており、2025年半ば時点で状態の良いボディは約$600 USDが相場です。これは新品の希少性によるもので、新品価格と大きな差はありません。入手性: X-T30 IIは技術的には現行機種ですが、多くの小売店が後継機を待っている状況です。富士フイルム公式ショップでも2025年初頭にはバックオーダーとなり、一部では在庫がなくなり次第、事実上ディスコンとの報告も。Adoramaでは2025年夏まで在庫なしとのユーザー報告もありました。新品のX-T30 IIが欲しい場合は早めの購入か、次期モデルを検討する必要があるかもしれません。(富士フイルムは「X-T30 II後継機」が2025年後半に登場することを示唆しています。)
- 富士フイルム X-E4: X-E4は$849 USD(ボディのみ)(27mmレンズ付きで$1049)で2021年3月に発売されました。発売当初は人気で、その後供給問題が発生し、意外にも比較的早期に生産終了となりました。2023年末には富士フイルムがX-E4の生産を終了し、米英の大手小売店では「新品は入手不可」と表示されました。これにより2024年には中古価格が高騰し、一時は中古X-E4ボディが$1200~1500(元の定価を大きく上回る)で出品される事態に。TikTokやレトロカメラブームによる需要増が要因です。2023年半ばには中古市場で「今は異常に高い」と評されました。2025年6月に後継機X-E5が発表されると、やや落ち着きましたが、新品のX-E4は一部地域の在庫を除きほぼ入手不可能です。もし見つかれば、まだ元の$849程度の値札が付いているかもしれませんが、基本的には中古を探すことになるでしょう。2025年半ばの中古X-E4ボディは状態によりますが$700~$900程度(ピーク時より下がったものの、依然として高値)。ヨーロッパでは中古で約€800が目安です。入手性: 実質的に生産終了。中古市場や、在庫を持つ小規模販売店が頼りです。X-Eシリーズの形状にこだわる場合は、X-E5が現行の選択肢ですが、こちらは大幅なアップグレードにより$1699とかなり高価です。
- Fujifilm X-S10: X-S10は本体価格999ドルで2020年後半に発売され、2022年にはセールで約899ドルになることが多くなりました。2023年に公式に生産終了となり、後継機のX-S20が発売されました(X-S20は2023年中頃に1,299ドルで登場)。その頃、多くの小売店がX-S10の在庫を一掃しました。2025年になると、大手店舗で新品のX-S10を見かけることはほとんどありませんが、一部のカメラショップやオンライン販売者が約800ドル前後で新品在庫を持っている場合もあります。中古のX-S10本体は簡単に見つかり、状態によって600~700ドルで取引されています。例えば、KEHやMPB(中古機材販売店)ではX-S10が600ドル台後半で掲載されています。X-S20がより高価なため、X-S10はIBISや富士フイルムの技術を手頃に手に入れる方法として依然として魅力的です。入手状況:実質的に新品は生産終了。新品にこだわりX-S10が見つからない場合はX-S20を検討することになります(こちらはかなり高価ですが、新プロセッサー、6K動画、大容量バッテリーなどが追加されています)。しかし、コスト重視なら中古のX-S10は2025年時点で富士フイルムのラインナップの中でも最もコストパフォーマンスの高い選択肢の一つで、しばしば「価格に見合う優れたミッドレンジカメラ」とレビューで評価されています。
主要な世界市場:
- アメリカ合衆国: 上記の米ドル価格が適用されます。Amazon、B&H、AdoramaではX-T30 IIが時折899ドルで在庫あり、X-E4は在庫切れ、X-S10は生産終了(小規模な小売店で799ドル前後で見つかる場合あり)。
- ヨーロッパ(ユーロ圏): X-T30 IIとX-E4は新品で約900ユーロ、現在は見つかれば同程度かやや安い程度。X-S10は新品で約950ユーロ、X-S20に置き換わり約1,299ユーロ。
- イギリス: X-T30 IIは本体769ポンドで発売、X-E4は799ポンド、X-S10は949ポンドで発売。生産終了前に実売価格はやや下落。2025年には、X-T30 IIが在庫があれば約700ポンド、X-E4は中古のみで約600ポンド以上、X-S10は中古で約500~600ポンド。
- アジア: 日本ではこれらの機種が人気で、新品がより長く見つかる場合もあります。例えばX-E4は日本で早期に生産終了とされましたが、東京の中古ショップではX-E5発表までプレミア価格で販売されていました。発売時の価格はX-T30IIが約95,000円、X-E4が約90,000円。
考慮すべき点: 新モデル(X-S20、X-E5、X-T50など)が登場したことで、旧モデルは最新センサーが不要ならお買い得
です。例えば予算重視なら、X-S10の中古が600ドルなら、手ブレ補正付き26MPカメラとして非常に高い価値があります。同様に、X-T30 IIが700ドル前後で見つかれば、X-T4と同等の画質をより安価で手に入れられる素晴らしい選択肢です(機能はやや少ないですが)。逆に、中古X-E4の価格が高騰しすぎて(1,000ドル近く)しまった場合、新品のX-E5(1,699ドルですが、機能は大幅に向上)にもう少し出して買う方が良いという意見もあります。しかし、多くの富士ユーザーはX-E4の独自性を愛しており、コレクターズアイテムとしての価値も上昇しています(「最後のその系統」という魅力)。
最後に、アメリカ在住なら富士フイルム公式のリファービッシュストアもチェックしましょう。時折リファービッシュ品が入荷します(例えば、富士公式サイトでX-T30 IIキットやX-S10キットがリファービッシュセールで販売されており、X-T30 II+15-45mmキットが約900ドルなど)。これらは保証付きで、良い中間選択肢となります。
要約すると:X-T30 II – 見つかれば約800ドルですが、在庫は限られており、販売終了が進んでいます。 X-E4 – 基本的に中古のみ、約800ドルを想定してください。販売終了により高額な出品にも注意が必要です。 X-S10 – 販売終了ですが中古は豊富、約600~700ドル。元値1000ドルと比べるとお買い得です。主な販売店:購入を検討している方のために、富士フイルム公式製品ページ(仕様や販売店検索あり)や一部販売店ページへの直接リンクを紹介します。
- Fujifilm X-T30 II 公式ページ(富士フイルムUSA)–「Shop Now」リンクから富士フイルムオンラインストアへ。主な販売店:B&H Photoでは在庫があれば899ドルで掲載中。Adoramaも同様の価格帯。Amazonは出品者によって異なり、最近ではサードパーティー経由で約1100ドルと、品薄を示しています。
- Fujifilm X-E4 公式ページ –(富士フイルムUSのリンクは公式サイトにありますが、販売終了のため非表示の場合あり)。販売店:B&Hでは販売終了と表示。Amazonではサードパーティーによる約1200ドルの出品があり、市場価格の高騰を裏付けています。
- Fujifilm X-S10 公式情報 – 富士フイルムUSAのアーカイブページ。販売店:B&Hなどでは実質的にX-S20に置き換えられています。X-S10を狙うなら中古が最適:MPB、KEH、eBayなど。
(価格は常に変動するため、必ず最新情報を確認してください。また、レンズ付きキットなどのお得なセット販売も検討しましょう。)
専門家の意見とレビュー要約
これらのカメラについて、専門家や経験豊富なレビュアーの意見を聞くのは参考になります。いくつかの注目コメントや見解を紹介します:
- X-T30 IIについて: 「見た目も良く、使っていて楽しい – Fujifilm X-T30 IIは初心者フォトグラファーにとって必要なものがすべて揃っているだけでなく、それ以上のものもある!」(DigitalCameraWorld)。エントリーモデルでありながら、その実力は上位機種に匹敵するとよく評価されています。PhotographyBlogはMark IIの進化点について、「高解像度LCD、1080p/240fpsスローモーション、フィルムシミュレーション2種追加、オートモードの改良、低照度AF性能の向上」と述べています。DPReviewの動画比較では、X-T30 IIとX-S10の画質は同等で、手ブレ補正かサイズかなど、好みや必要な機能で選ぶ形になったとしています。 結論: X-T30 IIはしばしばX-T4の性能をよりシンプルかつ安価な形で求める人にとって最適な富士機種として推奨されています。Amazonで富士のミラーレス機のベストセラーになったこともあり、その人気の高さがうかがえます。
- X-E4について: DPReviewは85% シルバーアワードを与え、次のように結論付けました。「X-E4は、優れた画質と便利な機能を備えたスタイリッシュなカメラです。ブランド最小のXマウント機で、ストリート、旅行、汎用の写真家にとって良い選択肢です… [ただし] X-E4が唯一得意でないのはAFトラッキングで、多くの競合機がより優れたトラッキングや顔・瞳検出を提供しています。」。つまり、想定される用途(カジュアルからエンスージアスト向けのコンパクト撮影)には最適ですが、アクション撮影を重視する人には物足りないかもしれません。多くのレビューはデザインを絶賛しました – 「富士フイルムはX-E4で少しミニマリズムに走りすぎたのでは?」とDPReviewは考察しましたが、タッチスクリーンのカスタマイズで対応できると認めています。PetaPixelのハンズオンレビューでは、X-E4は「本質的にレンズ交換式のX100V」と評され、その体験をより柔軟に提供していると述べられました。彼らや他のレビュワーは、X-E4があまりにも早く生産終了となったことの皮肉も指摘し、カルト的な人気を高めています。写真を美的体験として楽しみたいなら、X-E4はその期待に十分応えてくれます。ただし、ミニマルな操作系で工夫する覚悟は必要です。
- X-S10について: このカメラは多くの好意的な評価を集めました。DPReviewのレビューは86%と評価し、「Fujifilm X-S10は優れた汎用カメラです。高い画質、優れた動画性能と機能、高速連写… 唯一の懸念はAFトラッキングで、ライバルに遅れをとっています」とコメントしました。こちらもシルバーアワードを受賞しています。PetaPixelのレビュー(Ted Forbes氏)は「ウェルター級の挑戦者」と呼び、999ドルでノックアウト級の機能を実現したと強調しました: 「フラッグシップモデルと同等の高画質が得られ、Fujifilmは印象的な機能を盛り込んでいます… もちろん小さな妥協点(防塵防滴なし、バッファ小さめ)はありますが… この価格を考えれば素晴らしいパッケージです。」。特にエルゴノミクスと作りを称賛し、「オリンパスのコンパクトな良デザインを思い出させ、小型カメラとしてエルゴノミクスは抜群です。」と述べています。IBIS(ボディ内手ブレ補正)の搭載も大きな評価を受け、あるレビュワーは「X-S10はフラッグシップX-T4の多くの機能を提供している」(同じセンサー、IBIS、類似の動画機能)、「より小型・低価格なボディで」と述べています。 [20] [21]。X-S10は“隠れた名機”と見なす人も多く、Fujiのレトロボディほど「カリスマ性」はないものの、世代を代表する最高のコストパフォーマンスを持つ万能APS-Cカメラの一つと評価されています。ラボテストを行うRtings.comでは、X-S10は主にIBISと動画性能の優位性から、X-T30 IIよりもわずかに高く評価されました。
全体の雰囲気をまとめると:X-T30 IIは、その性能とクラシックなFujiの魅力のバランスで愛されています(「もし写真を最初からやり直すなら、リストの上位に入る」とある編集者)。X-E4は、コンパクトさとスタイルを重視する人々に支持されており(X100Vと並んでレトロレンジファインダーの喜びを提供する機種としてよく挙げられます)。X-S10は、おそらくほとんどの人にとってベストな選択肢として評価されており、手間なく素晴らしい写真や動画を撮りたい人に最適です – DPReviewフォーラムのコメントでは、「より優れたオールラウンドな体験が欲しいならX-S10を選ぶべき。そして、手ブレ補正があることで新たな世界が広がることを忘れずに」と述べられています。
次は何?– 富士フイルムの最新&今後登場予定のカメラ(X-T50、X100VI、X-Pro4 など)
富士フイルムは休んでいません――これらのモデルが登場してからも新製品が発売され、2024年後半や2025年に登場予定の新しいカメラへの話題がたくさんあります。ここで、現在のニュースや噂について簡単にまとめておきます:
- Fujifilm X-T50: X-T30 IIの後継機が2024年6月に登場し、「X-T40」ではなく、名称が一気にX-T50となりました。そして大幅なアップグレードです――実質的にX-T5の40MPセンサーとIBISをミドルレンジボディに搭載しています。X-T50は40.2MPのX-Trans CMOS 5 HRセンサー(X-T5と同じ)、最新のX-Processor 5、5軸ボディ内手ブレ補正を備え、最大6.2K/30pまたは4K/60p 10bitの内部動画撮影が可能です。つまり、「X-T5のほぼすべての機能を、はるかに小型のボディで提供」しています。さらに、X-S20のような新しいフィルムシミュレーションモードダイヤルも上部に追加されました。レトロなシャッターダイヤルはそのままに、内部はより現代的になっています。X-T50の発売価格は1,399米ドル(ボディのみ)で、X-T30 IIよりも高い位置づけです。富士フイルムのプレスリリースでは、ステップアップモデルとして紹介されています。比較する方のために、X-T50の主なスペック:メカニカル連写8コマ/秒(変更なし)、電子シャッター20コマ/秒(従来通り)、プロセッサー5による被写体検出AFの向上、バリアングル3インチ液晶、そしてついに――X-Txxシリーズで初めて防塵防滴仕様になりました。PhotographyLifeのレビューでは「この軽量な40MPカメラはX-T30 IIの後継機」と評され、CineDは「X-T5の機能を小型化…40MP、IBIS、6.2K動画…で$1399」と述べています。もし2025年にX-T30 IIを検討しているなら、X-T50がより多機能で登場していることを知っておいてください(ただし価格は高めです)。富士フイルムは、しばらくの間X-T30 IIもX-T50と併売し、低価格オプションを提供するとしていますが、X-T30 IIの在庫は徐々になくなるでしょう。予算に余裕があれば、X-T50は最先端技術を備えた魅力的な「新ミドルレンジ」モデルです。
- Fujifilm X100VI: 名高いX100Vの後継機が2024年2月に正式発表(Xサミット東京にて)され、その直後に発売されました。X100VI(X100シリーズ第6世代)は、非常に人気となり、すでにカルト的ヒットだったX100Vをも上回る人気となりました。主なアップグレード点:40MPセンサーとX-Processor 5を搭載し、富士フイルムの最新画質と同等になりました [22]。驚くべきことに、富士フイルムはIBIS(ボディ内手ブレ補正)を追加することに成功しました。これはX100シリーズの固定レンズ機で初めての手ブレ補正搭載です [23]。動画機能も向上し、X100VIは6.2Kオープンゲート動画(6240×4160、センサー全域3:2使用)を30pで、4Kは最大60p、10bit 4:2:2内部記録で撮影可能です [24]。他にも、内蔵4段NDフィルター、改良された0.5倍倍率のOVF/EVFハイブリッド、新しいチルト式LCD(ついにX100シリーズにチルト液晶が搭載)などの強化があります。レンズは23mm f/2のままですが、40MP解像度に合わせて光学的に若干の調整が加えられていると噂されています。X100VIの需要は非常に高く、富士フイルムの幹部・五十嵐祐司氏は「初日の予約数が非常に多く、一部の方は1年待ち…すでに1年で[過去のX100モデル]の3~4年分を売り上げた」と述べています。これによりバックオーダーと品薄状態(X100Vと同様)が発生しました。富士フイルムは生産を増強していますが、X100VIを手に入れたい場合は、ウェイトリストに並ぶかプレミア価格を支払う覚悟が必要です。希望小売価格は1,599米ドル(ボディ=固定レンズカメラ)です。X100VIは、X-E4/X-T30 IIの代替や補完としても魅力的で、独自の魅力を持つコンパクトな一体型カメラとして多くの人を惹きつけています。X100Vブームを逃した方には、X100VIが新たな注目機種ですが、しばらくは入手困難が続くでしょう。X100VIの成功は間接的にX-E4にも影響を与えました。X100V/VIを手に入れられなかった人が、次善の策としてパンケーキレンズ付きのX-E4に流れたためです。今後、X100VIが登場したことで(入手困難ではありますが)、多少の動きが見られるかもしれません。
- 富士フイルム X-Pro4(または X-Pro5?): X-Proシリーズには熱心なファンがいて、2019年のX-Pro3以来ずっと待ち続けています。富士フイルムはX-Pro3の後継機が開発中であることを認めており、「我々の計画は変わっていない」とX-Proシリーズについて述べています。しかし、2025年8月時点でまだ発売されていません。富士が「X-Pro4」という名称を飛ばしてX-Pro5と名付けるのでは、という憶測もあります(発売時には新しい40MPセンサーとX-Processor 5を搭載する可能性が高いため、5世代目のセンサーに合わせるため)。「必ずしもX-Pro4と呼ばれるとは限らない…実際にはX-Pro5になるかもしれない」とDigital Camera Worldは指摘しています。発売時期はやや流動的で、多くのアナリストは2025年後半から2026年初頭にX-Pro3の後継機が登場すると予測しています。FujiRumorsは2025年の発売は期待しない方がよい、2026年になる可能性が高いと示唆しています。なぜ遅れているのでしょうか?おそらく富士はX-Pro用に26MP世代をスキップし、新技術を取り入れるのを待った(パンデミックや供給遅延もあった)ためです。ファンは新機種に何がもたらされるかに期待しています。確実にハイブリッド光学/電子ビューファインダーは継続され、富士の幹部はX-Pro3で採用された隠しリアスクリーン(下に開き「フィルムシム」サブモニターが付いていた)など独自要素も維持することを示唆しています。防塵防滴、X-T5と同じ40MPセンサー、AFの向上なども期待できます。中には富士がモノクロ専用X-Proバリアントのような大胆なことをするのではと推測する声もあります(あくまで憶測)。いずれにせよ、レンジファインダースタイル愛好家は新しいX-Proに注目しています。それまでは、X-Pro3自体は生産終了しているものの多くの人に評価されていますが、耐久性の問題(リアLCDケーブルの故障)があったことに注意が必要で、富士はこれに対応しており新モデルの設計にも影響するかもしれません。
- その他の富士ニュース: 富士フイルムは多忙です。2022~2023年に40MPのX-H2と26MP積層型のX-H2S(ハイエンドモデル)、X-T5(40MP、実質的にレトロ操作系のミニX-H2)を発売し、2023/24年には下位モデルのX-T5世代:X-S20(X-S10の後継、X-Processor 5搭載、同じ26MPセンサーだがバッテリー大幅改善・6.2K動画・Vlogモード追加、$1,299)とX-E5(2025年8月に発売)。X-E5は特に注目で、X-E4から大きく進化:40MPセンサーとIBISを小型ボディに搭載し、実質「X-Pro lite」となっています。価格もそれに見合い高め(ボディ$1699)。初期レビュー(例:PetaPixel)では「X-E5は内部的にはX-T50を小型化したもの。同じ優れた40MPセンサー…5軸IBISも搭載」と評価されています。つまり富士はミドルクラス機のスペック(と価格)を明らかに上位化しています。2025年にX-E4、X-T30 II、X-S10で迷っている人は、これらの新しい選択肢も知っておくべきです:レンジファインダースタイルが好きで予算が許せばX-E5、X-T系で最新技術が欲しければX-T50、動画やバッテリー重視ならX-S20(X-S20はバッテリーが大きくなりX-S10の2倍の撮影枚数)。
- 他モデルの噂:X-T100系の復活やX-Mシリーズ(エントリー向け)についても話題があります。実際、富士は2024年に一部市場でX-M5を発売しており、これは新プロセッサーを搭載したX-T200の後継機です。ただし、これらはややニッチな存在です。愛好家が主に注目するのはX100(既に紹介済み-X100VIが登場し大人気)とX-Pro(いずれ登場予定)です。また中判GFXも新製品(2023年GFX100 II、2025年GFX「Eterna」ビデオカメラなど)が出ています。しかしAPS-Cミラーレスでは、すべてを第5世代プラットフォームへ移行することが焦点となっています。
まとめると、Fujifilmの2025年ラインナップはより高級志向にシフトしています。ミドルクラスのモデルにもフラッグシップのセンサーやIBISが搭載されるようになりましたが、価格も上がっています。この比較記事を読んでいる方へ――もし予算に余裕があり、将来性のあるスペックを求めるなら、X-T50やX-E5、X-S20を検討してください。これらは40MPの高解像度(大きくプリントしたり大きくトリミングする場合に最適)、より優れたオートフォーカス(動物や乗り物などのAI被写体検出を含む)、そしてバッテリー寿命の向上(X-S20は新型バッテリーを搭載)などを提供します。しかし、もしコストパフォーマンスを重視するなら、X-T30 II、X-E4、X-S10は2025年でも非常に有力な選択肢です。これらは新モデルの価格の一部で、ほとんどの写真家が必要とする機能の90%を提供します。26MPセンサーも十分に優秀で、テストも重ねられており、40MPよりも低照度での画素サイズを好む人もいます。これら旧モデルは中古市場での入手性や価格面でも有利で、愛好家にとって賢い選択肢となります。
まとめとして:Fujifilm X-T30 II、X-E4、X-S10は、それぞれ富士フイルムの魅力を異なる形で表現しています――ダイヤル満載のレトロな一眼スタイル、ミニマルなレンジファインダー、そして現代的な万能型。2025年においても、これらは写真や動画制作に優れたツールであり、充実したレンズシステムと富士フイルムのXマウントへの継続的なサポートに支えられています。あなたの撮影スタイル――旅のストーリーテラー、ストリートフォトの純粋主義者、あるいはハイブリッド志向のビギナー――に応じて、どれかがぴったりと感じられるはずです。そして、富士フイルムの新製品が控えている今、いつでも明確なアップグレードパスが用意されています。楽しい撮影を!
出典:
- Fujifilm X-T30 II – DPReview の仕様およびレビューコメント;PhotographyBlog の比較。
- Fujifilm X-E4 – DPReview レビュー(サイズ、画質、AFの結論);PetaPixel のファーストインプレッション。
- Fujifilm X-S10 – DPReview レビュー(結論);PetaPixel レビュー(Ted Forbes);DigitalCameraWorld のカバレッジ。
- 機能・仕様の参照 – DPReview および Imaging-Resource の仕様ページ(連写速度、EVF仕様など) [25];CineD およびX-T50・X100VIの富士フイルム公式リリース [26]。
- 価格・入手性 – Amateur Photographer の生産終了ニュース;Fuji Rumors / FujiXWeekly の中古価格情報;B&H の小売リスト。
- 今後のモデル – DigitalCameraWorld「カメラ噂 2025」(富士フイルムの項目);DPReview のCP+ 2025インタビュー;Fuji Rumors および Reddit のX-Proラインに関する議論。
References
1. www.dpreview.com, 2. www.dpreview.com, 3. www.dpreview.com, 4. www.dpreview.com, 5. www.dpreview.com, 6. www.dpreview.com, 7. petapixel.com, 8. www.fujifilm-x.com, 9. www.fujifilm-x.com, 10. www.dpreview.com, 11. www.dpreview.com, 12. www.dpreview.com, 13. www.dpreview.com, 14. petapixel.com, 15. www.dpreview.com, 16. www.dpreview.com, 17. www.dpreview.com, 18. www.dpreview.com, 19. www.dpreview.com, 20. www.dpreview.com, 21. www.dpreview.com, 22. www.cined.com, 23. www.cined.com, 24. www.cined.com, 25. www.dpreview.com, 26. www.cined.com