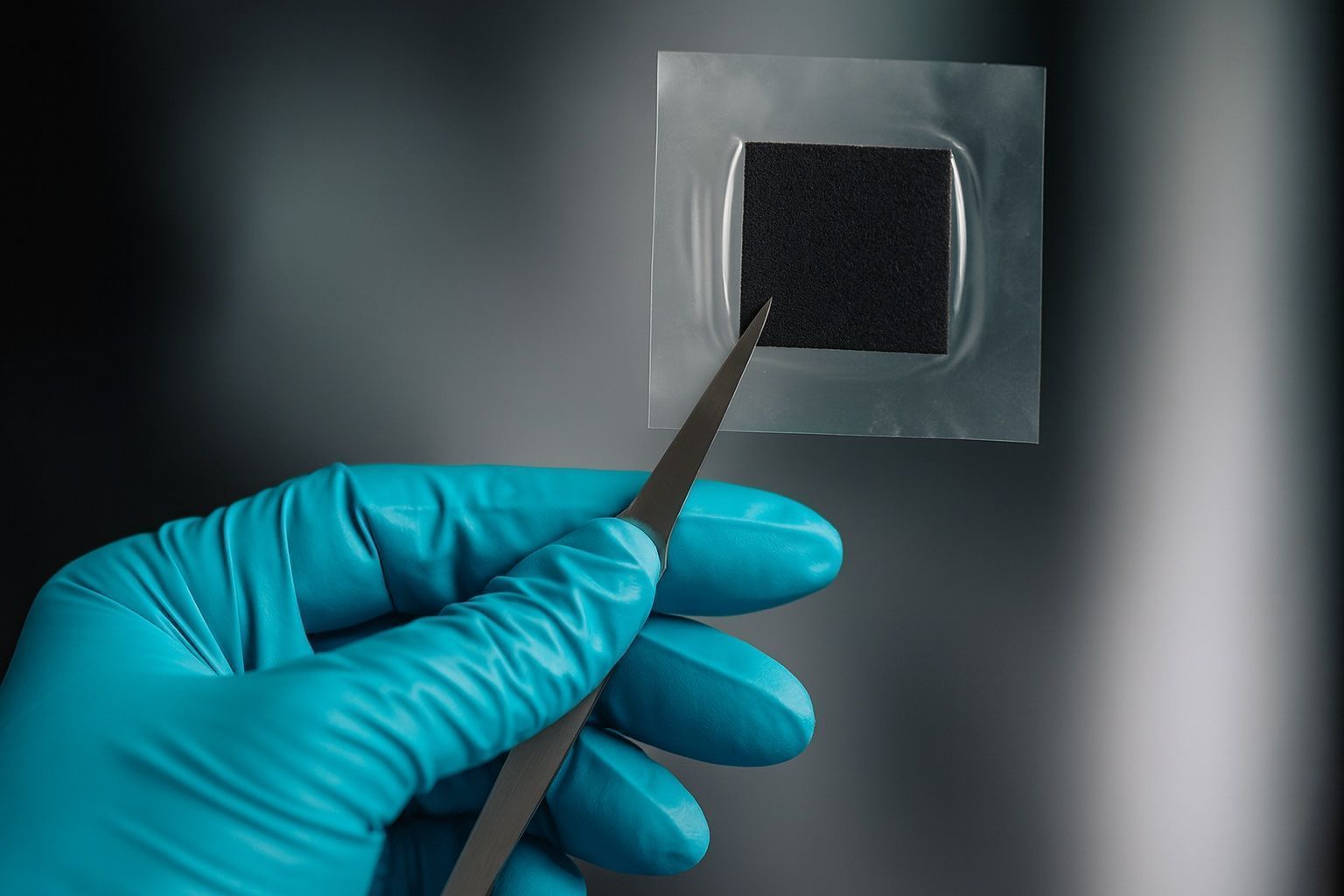- PEM・アルカリ・SOECの3技術はそれぞれ固体高分子膜、液体電解質のKOH、固体酸化物電解質を用い、動作温度は約50–80°C(PEM)、60–100°C(アルカリ)、700–850°C(SOEC)である。
- SOECは700–850°Cの高温で酸化物イオンを伝導するセラミック電解質を使い、水蒸気をカソードへ供給して水素を生成する。
- 通常の全量産条件での水素生産効率はアルカリとPEMがほぼ同等で1kgあたり約55–60kWh、約55–65%のエネルギー効率とされ、SOECは熱を外部熱源と組み合わせると80%台の効率を達成できる。
- 変動する再エネ入力への対応ではPEMが起動・応答が速く最も適しており、アルカリは加圧型設計で改善されつつ、SOECは高温ゆえ頻繁な電源変動には不向きとされる。
- CapExはアルカリが最安で、IEAはアルカリ約$2,000/kW、PEM約$2,450/kWと報告、ただし中国市場では$750–$1,300/kWまで低下するケースがあり、SOECのパイロットは$2,000–$3,000/kW、量産で数百$/kWまで下がる可能性がある。
- 運転コストは主に電力コストで、PEMは高負荷運転で効率・耐久性のトレードオフ、アルカリは低コスト・長期安定性が特徴となる。
- 寿命とメンテナンスではアルカリが60,000–90,000時間、Sunfireは90,000時間超えの実績、PEMは60,000–80,000時間を目標に、SOECは現状20,000時間程度で40–60,000時間を目指す。
- 商用化状況はアルカリとPEMがTRL9で広く普及、SOECはTRL7–8の実証段階で、Sinopec新疆260MWアルカリ施設、Shell Refhyne IIの100MW PEM、Nesteの2.6MW SOEC、NASA Amesの4MW SOECなどの実例がある。
- 主要メーカーと代表モデルには、アルカリのThyssenkrupp Nucera(NEOM向け2GW)、NelのA-Series、John Cockerillの5MWモジュール式加圧アルカリ、Cummins HyLYZER、PEMのSiemens Energy Silyzer、ITM Power HGAS、Plug Power、EnapterのAEMモジュールなどが挙げられる。
- 今後の技術動向として、Hysataの毛細管供給型電解セルの80%(LHV)効率、AEMの普及、Siemensの1000cm²超セル面積開発によるSilyzer 300アップグレード、Enapterの量産AEMモジュール展開などが注目されている。
水素電解装置はグリーン水素革命の中心にあります。この包括的な比較では、3つの主要な水電解技術—プロトン交換膜(PEM)、アルカリ性、および固体酸化物(SOEC)電解装置—について、それぞれの仕組み、効率、コスト、耐久性、2024~2025年時点での最新動向を詳しく解説します。また、どの技術が間欠的な再生可能エネルギーに適しているか、市場のリーダーは誰か、今後登場する新しいイノベーション、環境面での考慮事項、そして専門家がこれらの電解装置の将来について何を語っているかも見ていきます。
動作原理と化学反応
アルカリ性電解装置: アルカリ性システムは最も古く、最も確立された電解装置技術です。液体電解質(通常は水酸化カリウム、KOH)とニッケル系電極を使用します。電流を流すと、カソード側で水が分解されて水素ガスと水酸化物イオン(OH⁻)が生成されます。OH⁻イオンは電解質を通ってアノード側に移動し、そこで酸素ガスと水に再結合します [1] [2]。全体の反応は単純に水がH₂とO₂に分解されるものです。電解質が液体であるため、アルカリ性セルは通常、中程度の温度(100°C未満、一般的には約60~80°C)で動作します [3] [4]。この成熟した設計は何十年も使用されており(例:クロルアルカリ工業や肥料工場)、その堅牢性とシンプルさで知られています。アルカリ性電解装置から得られる水素は高純度ですが、微量の水分やKOHが含まれることがあるため、燃料電池グレードの水素には下流での精製が必要な場合があります [5]。
プロトン交換膜(PEM)電解槽: PEM電解槽は、電解質として固体高分子膜(プロトン交換膜)を使用します。水はアノード側に供給され、そこで酸素、プロトン(H⁺)、電子に分解されます [6]。膜はプロトンのみを伝導するため、H⁺イオンは膜を通ってカソード側へ移動します。そこで、外部回路を通じて供給された電子と再結合し、水素ガスを生成します [7]。PEM自体がガスの混合を防ぐため、カソード側で非常に高純度(しばしば99.999%以上)の水素が得られます [8] [9]。PEM電解槽は、アルカリ系と同様に比較的低温(通常約50~80°C)で動作します [10]。アノードにはイリジウム、カソードには白金といった貴金属触媒と、高純度の水供給が必要です。固体電解質と高速なプロトン輸送により、迅速な応答と起動が可能で、PEMユニットは非常に柔軟な運転ができます [11] [12]。
固体酸化物電解槽(SOEC): 固体酸化物電解セルは根本的に異なる方式で動作します。高温(一般的に700~850°C)で、酸素イオン(O²⁻)を伝導する固体セラミック電解質を使用します [13] [14]。液体の水の代わりに、水蒸気がカソードに供給されます。そこで水蒸気(H₂O)は還元され、電子を受け取り水素ガス(H₂)と酸素イオンに分解されます [15]。O²⁻イオンはセラミック電解質を通ってアノードに移動し、そこで電子を放出してO₂ガスを生成します [16]。本質的に、SOECは固体酸化物燃料電池の逆であり、電気(と熱)を使って水蒸気をH₂とO₂に分解します。高温での運転により、エネルギー入力の一部が熱として供給され、生成される水素1kgあたりの必要な電気エネルギーが低減されます。SOECはしばしば産業プロセスや集中的な熱源(原子力発電所さえも)からの廃熱を活用して効率を向上させます [17] [18]。その代償として、複雑なセラミック材料と高い運転温度の維持が必要となります。(特に、500~600°C程度の中温セラミック電解に関する研究開発が進行中ですが [19]、現在の商用SOECユニットは依然として約750°C以上で稼働しています。)
効率と運転温度
電気効率: 実際には、従来型のアルカリおよびPEM電解槽は同等の効率を持っています ― 一方が本質的に他方より効率的であるという認識とは異なります。同等の条件(フル負荷時のシステム全体効率)で比較すると、「ほとんどすべてのPEMおよびアルカリ効率は同じ範囲内にある」 [20]。一般的な商用システムでは、水素1kgあたり約55~60kWhの電力が必要であり、これは約55~65%の効率(低位発熱量基準)に相当します。つまり、アルカリ型もPEM型も1kgの水素(LHVで約33kWhのエネルギーを含む)を生成するのに60kWh弱を消費します。各技術には設計上の違いがあります ― 例えば、アルカリセルは非常に高い電流密度で効率が低下する場合があり、PEMシステムは部分負荷時にわずかに高いピーク効率を示すことがあります ― しかし実際の平均性能は同等です [21] [22]。数十件のプロジェクトからの最新データでは、すべての損失(スタック+バランスオブプラント)を考慮した場合、アルカリおよびPEM電解槽は同じ効率帯に集まっていることが示されています [23]。
高温SOEC効率: 固体酸化物電解槽(SOEC)は、水を分解する作業の一部に熱を利用することで、より高い電気効率を達成できます。実際、適切に運転されたSOECは、同等サイズのPEMやアルカリ型ユニットよりも、入力電力1kWあたり20~25%多くの水素を生成できます [24]。例えば、2023年にNASAで稼働した4MWのBloom Energy SOECシステムは、低温(PEM/AWE)電解よりも25%高い効率で水素を生成したと報告されています [25]。ドイツのSOEC開発企業Sunfireも同様に、廃熱を利用することでマルチメガワットSOECユニットで約84% LHV効率を達成しました [26]。ただし、SOECの効率的な優位性は高温蒸気が利用可能な場合のみであることに注意が必要です。蒸気を生成するためのエネルギーは依然として必要です。SOECに外部で加熱された蒸気(例:産業廃熱や原子炉の熱)を供給した場合、1kgの水素あたりの電力消費量はPEM/アルカリ型システムよりも大幅に低くなります [27] [28]。外部熱源がない場合、SOECは自身の入力電力の一部を加熱に使う必要があり、純効率は低下します。まとめると、SOECは3方式の中で理論上最も高い効率(80%以上のオーダー)を提供しますが、そのレベルに到達するには電解槽と熱源の統合が必要です。
動作温度範囲: 動作温度は主要な差別化要素です:
- アルカリ型: 多くの設計で約60~100°C [29] [30]。この中程度の温度は液体電解質で良好なイオン伝導性を得るために必要ですが、一般的な材料(鋼、ニッケル)でも容易に対応できる低さです。
- PEM: 約50~80 °C、場合によっては約90 °Cまで [31] [32]。PEMシステムはアルカリ性よりやや低温で動作します。これはポリマーメンブレンの導電性と耐久性がその範囲で最適だからです。低温動作のため、起動や停止が迅速に行えます。
- SOEC:酸化物イオンセラミックスの場合は約700~850 °C [33] [34]。この高温には特殊なセラミックセルと断熱材が必要です。また、SOECは冷えた状態から素早くオン/オフできない—通常は熱いまま維持する(またはゆっくり加熱する)必要があり、熱衝撃を避けます。
資本コスト(CapEx)と運用コスト(OpEx)
資本費用: アルカリ電解槽は、シンプルで低コストな材料の使用と数十年にわたる製造経験により、初期費用で優位性があります。最近の分析では、アルカリシステムは3つの技術の中で最も低いkWあたりのCapExとなっています。例えば、国際エネルギー機関(IEA)は、アルカリ電解槽の設置コストは約$2,000/kW、PEMシステムは約$2,450/kWと報告しています [35]。(中国のようにアルカリユニットが大量生産されている市場では、アルカリスタックの価格は$750~1,300/kWまで下がることもあります [36]。)このコスト差は、PEMの高価な膜と触媒によるものです。PEM電極はイリジウムやプラチナなどの白金族金属を使用し、膜自体も高価なパーフルオロ化ポリマーです。これらの特殊材料が、PEMシステムを現在のプロジェクトでアルカリより約20%高価にしています [37]。とはいえ、PEMのコストは急速に低下しており、製造(未設置)ベースでは、最近のPEMシステムは低生産量で$700~1,100/kWと推定されており [38]、アルカリの$500~750/kWの範囲と大きく変わりません [39]。PEM技術の規模拡大に伴い、専門家はこの差が縮まると予測しています。実際、中国のあるPEMメーカーは、2030年までにPEM電解槽のコストがアルカリの約2倍程度(従来は数倍高かった)になると予測しています [40]。
固体酸化物電解槽(SOEC)はまだ大規模生産されていませんので、現時点での設備投資コスト(CapEx)は高いです。現在のパイロット規模のSOECユニットは、$2,000~$3,000/kWの範囲で見積もられています [41]。しかし、技術の成熟とともに大幅なコスト削減が期待されています。Bloom EnergyやTopsoeのような企業は、2020年代後半までにSOECを自動化ラインで大量生産することを目指しており、長期的には1kWあたり数百ドル台までコストが下がる可能性があります [42] [43]。まとめると、アルカリ型は初期費用が最も安く、PEMは現時点で約20~30%高く、SOECは現在最も高価(パイロット規模の価格)ですが、今後の改善が見込まれています。
運転コスト: どの電解槽でも運転コストの大部分は電力です。そのため効率が重要であり、効率が5%違うだけで、電力が高価な場合は水素1kgあたりのコストが大きく変わります。この点で、SOECの効率の優位性は、安価な熱が利用できる場合(蒸気用)、水素1kgあたりの電力コストを低減できます。PEMとアルカリ型では効率がほぼ同じなので、水素1kgあたりの電力コストもほぼ同じです。代わりに、運転コストの違いはメンテナンスやスタック交換(次のセクション参照)、および電解槽の運転方法(定常運転か変動負荷か)によります。ひとつの注意点として、PEM電解槽はしばしば高い電流密度(セル面積あたりの水素生成量が多い)で運転できますが、その分効率がやや低下し、劣化も早くなります [44]。運転者は、PEMスタックをやや高負荷で運転して(小型ユニットからより多くの水素を得る)、または効率重視で負荷を下げて運転するかを選択できます。これは設計・運用上のトレードオフです。一方、アルカリ型システムは、より大きなセル面積を使用し、1cm²あたりの電流をそれほど高くしないため、物理的に大型化しますが、長期的な安定性にも寄与します。
メンテナンスコスト(部品交換、作業費)も運転コストに影響します。アルカリ型システムは、液体電解質の定期的な管理(例:KOHのろ過や交換)やポンプ・シールのメンテナンスが必要な場合がありますが、PEMシステムは液体の取り扱いを避けられる一方で、水を超純水に保つためのイオン交換カートリッジや膜の状態の厳密な監視が必要です。寿命については後述しますが、もしPEMスタックの交換頻度がアルカリ型より高ければ、その分運転コストが増加します。一方、アルカリ型システムはしばしば下流のガス精製(KOHミストの除去や酸素純度の確保など)が必要で、これにはわずかな効率低下とメンテナンスコストが発生しますが、PEM水素は設計上、超高純度です [45]。
寿命とメンテナンス要件
最も重要でありながら難しい比較の一つは、電解槽スタックの耐久性と、その寿命中に必要なメンテナンスです。
アルカリ型の寿命: 従来型のアルカリ電解槽は長寿命で知られており、産業用途での数十年にわたる運転実績から、数万時間の稼働が可能です。メーカーはしばしば、スタックの寿命を大規模なオーバーホールまで60,000~90,000時間(連続運転で7~10年)としています [46]。実際、Sunfire社は最新の加圧アルカリユニットが現場で90,000運転時間を超えたと報告しています [47]。この耐久性の一因は、比較的穏やかな運転条件(KOHが一定のため電極で極端なpH変化がなく、中程度の温度)と、ステンレスやニッケルなどの堅牢な材料の使用にあります。アルカリ電解槽のメンテナンスは一般的に簡単と考えられています。業界分析の一つでは「この技術は監視、保守、運転が容易」と指摘されています [48]。電解液濃度の定期的なチェックや消耗品(シール、セパレーター、または炭酸化した場合の電解液)の交換が一般的です。多くのアルカリシステムは一般的な工具で現場保守が可能で、特殊な取り扱いが必要な壊れやすい膜材料も含まれていません [49] [50]。ただし、アルカリ電極は長期間で腐食することがあり、電極の劣化や不純物の蓄積により性能が徐々に低下する場合があります。スタックが寿命に達した場合、主なメンテナンス作業は(例えば電極板の交換などの)交換やオーバーホールとなります。
PEMの寿命: PEM電解装置は新しい技術であるため、歴史的には寿命が短い傾向がありました。初期のPEMスタックは、著しい劣化が起こるまでにわずか20,000~40,000時間しか持たないこともありました。しかし、近年の進歩により耐久性は大きく向上しています。最新のPEMスタックは、現在60,000~80,000時間の運転 [51](最適条件下で7~9年)を目指しています。それでも、PEMは同等サイズのアルカリ型よりもやや寿命が短いと考えられています [52] [53]。制限要因には、膜の化学的劣化、触媒層の摩耗(特に負荷が頻繁に変動する場合)、薄い高分子膜への機械的ストレスなどがあります。PEMスタックは非常に純度の高い水を必要とし、不純物があると膜や触媒が汚染されるため、水の浄化システムの維持が不可欠です。メンテナンス面では、PEMシステムは可動部品が少なく(多くの設計で液体電解質循環ポンプが不要、水供給が簡単なため)、しかしより専門的な対応が必要です。PEMの膜-電極接合体(MEA)の交換は繊細な作業であり、通常はリファービッシュセンターやOEMによって行われ、一般的な工場の作業場では行われません。貴金属触媒が必要なため、寿命終了時にこれらの触媒をリサイクル・回収することが重要です(コスト要因であると同時にリサイクルの機会でもあります)。全体として、PEMのメンテナンスはアルカリ型よりも複雑でコストが高い傾向があると業界関係者は指摘しています [54] [55]。これは部品(膜、触媒)のコストが高いことと、それらをサービスするための専門的な労働力が必要なことの両方を含みます。メーカーは、膜の寿命を延ばし、より安価でモジュール式のスタック設計を開発することで、これに対応しています。
SOECの寿命: 固体酸化物電解槽(SOEC)はまだ商業化の初期段階にあり、耐久性が最大の課題の一つです。800°Cでの運転は熱応力や材料劣化を引き起こし、スタック寿命を短くする可能性があります。現在のSOEC実証機では、20,000時間(わずか数年)で大きな性能低下が報告されています [56]。目標は、さらなる研究開発により40,000~60,000時間に到達することです [57]。SOECの故障モードには、熱サイクルによる亀裂、電極の焼結や中毒、シールの故障などがあります。これらの課題のため、SOECスタックは技術が成熟するまで、より頻繁な交換が必要になるかもしれません。メンテナンスについて: SOECシステムは複雑で、高温断熱材、熱交換器、場合によっては蒸気発生装置が必要です。つまり、保守が必要な補助部品(起動用のバーナーや電気ヒーター、熱風ブロワーなど)が多くなります。スタックの予期しない冷却や再加熱はセルにストレスを与えるため、運転者はSOECスタックをできるだけ温度を保ち、必要なら低出力でアイドリングさせ、頻繁なシャットダウンを避けます。高温材料(セラミックセル、特殊合金製インターコネクト)は金属ほど簡単に扱えず、スタックが故障した場合は通常ユニット全体を交換する必要があります。BloomやSunfireのようなメーカーは、固体酸化物燃料電池(SOFC)での経験を活かしてSOECの寿命延長に取り組んでいます。例えば、BloomのSOECユニットは、現場で数十億セル時の実績があるSOFCと同じセルプラットフォームを使用しています [58]。初期の結果は有望で、Bloomの4MWパイロットはフル負荷で4,500時間安定した性能を維持しました [59]。技術の進歩とともに、SOECのメンテナンス間隔は他の電解槽に近づくと期待されますが、現時点では、SOECはより頻繁なスタック交換と慎重な熱管理が必要となる可能性が高いです。
間欠的な再生可能エネルギーへの適合性
電解槽を間欠的な再生可能エネルギー(太陽光、風力)と統合することは、真に「グリーン」な水素を生産するための重要な用途です。電解槽の種類によって、変動する電力入力への対応が異なります:
- PEM電解装置は非常に柔軟性が高く、変動する電力への対応に優れています。起動や応答が速いため、待機状態からフル出力まで数秒~数分で立ち上げることができます [60] [61]。このため、急激な変動がある太陽光や風力発電との直接連携に最適です。また、幅広い負荷範囲で効率的に運転でき、容量の10%や20%でも、PEM電解装置は大きな効率低下や損傷リスクなしに水素を生産できます。この広いダイナミックレンジは、再生可能エネルギー統合の大きな利点です。実際、PEMユニットは余剰電力を動的に吸収したり、太陽光発電の発電カーブに分単位で追従したりする用途で使われています。
- アルカリ電解装置は従来、立ち上がりが遅く、安定運転に最適でしたが、近年の設計で大きく改善されています。従来のアルカリシステムは、ウォームアップや安定化に時間が必要でした。また、急激な電力変化は問題を引き起こす可能性があり、例えば電解液中の気泡や圧力変動などが発生していました。新しい「加圧型アルカリ」電解装置は、これらに対応する機能を追加しており、高圧で運転し、内部のガス分離性能も向上しているため、より速い立ち上げや頻繁なサイクル運転が可能です [62] [63]。メーカーによれば、先進的なアルカリユニットは、現在では「変動する再生可能エネルギー」の負荷プロファイルにも従いやすくなっています [64]。とはいえ、アルカリ技術は依然として一般的にPEMよりも起動や出力調整が遅い [65]。例えば、風力発電所が突然50%から100%出力に上がった場合、PEM電解装置は即座に追加電力を受け入れられますが、アルカリシステムは制御された立ち上げが必要になるかもしれません。非常に頻繁なオンオフサイクルや、電解装置がアイドル状態から毎日立ち上がるような用途では、PEMが好まれることが多いです。アルカリも再生可能エネルギーと十分に連携可能で、実際2023~2024年の大規模な太陽光発電H₂プロジェクトの多くはアルカリ型ですが、電解装置はより定常運転(短時間の変動は小型バッテリーで緩衝したり、電解装置を過度にサイクルさせずに太陽光出力を少し抑制したりする)で運用されることが多いです。
- SOEC電解装置は、現状では間欠的な運転にはあまり適していません。SOECは高温(数百度)を維持する必要があるため、日が沈んだり風が止んだりした際に完全に電源を切るのは現実的ではありません。頻繁な熱サイクルは寿命を大幅に短くしてしまいます。そのため、SOECは一定の電力源(例:原子力、地熱)や、安定した廃熱源を利用できる産業拠点での使用が想定されています。再生可能エネルギーと組み合わせる場合、SOECは電力入力が低下した際に温度を維持するため、何らかのエネルギー貯蔵や補助加熱が必要になるかもしれません。しかし、動的運転が不可能というわけではありません。Bloom Energyは、自社のSOECが100%出力から5%まで10分以内で出力を下げても悪影響がなく、低負荷時でも効率が高いことを実証しました [66]。これは、SOECプラントが高温を維持できれば(例えば熱を蓄える、またはハイブリッド加熱システムを使うなど)、水素の生産量をある程度調整できる可能性を示唆しています。しかし実際には、SOECは比較的安定した高稼働率の運転に最適であり、PEM(および改良型アルカリ)は、より間欠的な電源への直接接続に適しています 。
まとめると、PEMは応答が速く部分負荷効率も高いため、間欠的な再生可能エネルギープロジェクトの最有力候補です [67] [68]。アルカリ技術も、加圧型やより動的な設計によって進化しており、多くの再エネ主導システム(特に多少の遅延やバッファリングが許容できる大規模プラント)で実用的になっています [69] [70]。一方、SOECは現時点では連続運転用途が主なターゲットですが、将来的な技術革新やハイブリッド構成の活用によって、特定の状況下で変動電力にも対応できる可能性があります
。商用化状況と用途事例
アルカリおよびPEM電解装置の両方は完全に商業化されており(TRL 9)、世界中で広く導入されています。アルカリは産業用水素の主力技術であり、アンモニア製造、石油精製(加水素プロセス)、フロートガラス製造、化学品などの用途で半世紀以上使用されています。多くの古い設備は小規模(数MW)でしたが、アルカリ装置は拡大されてきました。100MWを超える複数のアルカリプロジェクトが進行中または稼働中です。実際、アルカリ技術は現在、新規電解装置容量の約70~90%を毎年占めています [71] [72]
固体酸化物(SOEC)技術は商業化の瀬戸際にあります。現在は実証段階(TRL 7–8)にあり、複数のマルチメガワット級パイロットがそのコンセプトを証明しています [73] [74]。例えば、2023年にはオランダのNeste石油精製所に2.6MW SOEC電解装置が設置されました——当時、世界最大のSOECシステムでした [75]。その数週間後、Bloom Energyはカリフォルニア州のNASAエイムズ研究センターでさらに大規模な4MW SOECシステムを稼働させました [76]。これらのプロジェクトは、SOECが産業環境に統合できること(Nesteは水素を精製プロセスで使用予定)や、マルチMW規模に拡張できることを示しました。SOECのユースケースは、安価な熱や蒸気が利用可能な場合にその高効率性を活かせる点にあります。精製、石油化学、製鉄所など高品位の廃熱を持つ産業は、SOEC電解装置の設置に最適な候補です。もう一つの新たなユースケースは共電解で、SOECが蒸気とCO₂を同時に電解して合成燃料生産用の合成ガス(H₂とCOの混合物)を生成できます。Sunfireのような企業がこのプロセスでe-燃料の製造を実証しています。まだ広く普及してはいませんが、共電解は持続可能な航空燃料やプラスチック分野のゲームチェンジャーとなる可能性があり、SOECは(CO₂還元に十分な高温で動作するため)この用途に独自の適性を持っています。
注目すべきユースケースと導入事例:
- 大規模グリーン水素プラント: アルカリ電解装置は再生可能エネルギーと連携した「水素ファーム」に導入されています。中国は大規模プロジェクトで先行しており、例えば新疆のSinopecグリーン水素施設では、太陽光発電所による電力で260MWのアルカリ電解装置を稼働させています。2023年に稼働し、年間2万トンの水素を近隣の精製所に供給し、天然ガス由来の水素を代替します [77] [78]。これは現在、世界最大の単一電解装置プラントです。同様に、サウジアラビアのNEOMプロジェクト(建設中)でも、数百MW規模のアルカリ電解装置を用いて輸出用のグリーンアンモニアを生産予定です。これらのプロジェクトは、スケールメリットからアルカリ方式を採用しています。
- グリッドバランシングとパワートゥガス: PEM電解装置は、余剰再生可能電力の吸収が重要となるプロジェクトで使用されています。ドイツでは、いくつかのパワートゥガス拠点がPEMスタックを用いて余剰風力発電を水素に変換し、それを天然ガス網に注入したり、メタン化したりしています。PEM電解装置は急速に出力を上下できるため、グリッド周波数調整サービスにも理想的です。ヨーロッパの10~20MW級PEMシステム(例えばShellのRheinland製油所のREFHYNE 10MWプラントなど)は、水素供給源であると同時に、地域グリッドのバランスを取る柔軟な負荷としても機能しています。
- 輸送と水素充填: 多くの水素ステーション(燃料電池車向け)では、現地にPEM電解装置が設置されています。Nel Hydrogenのような企業は、ステーションにコンパクトなPEM電解装置モジュールを展開しており、高圧かつ超高純度のH₂を直接車両タンクに充填できるようにしています [79] [80]。PEMの設置面積の小ささと高純度はこの用途で重要です。対照的にアルカリ型システムは通常、低圧で水素を生成するため(充填用途には外部コンプレッサーが必要)、また微量の水分やアルカリ成分が混入する可能性があり追加の精製が必要となるため、PEMが輸送用水素充填分野で主流となっています。
- 産業用オンサイト水素: 現在水素ボンベや液化水素をトラック輸送している多くの産業が、信頼性やコストの観点からオンサイト電解装置に切り替えています。ここでは規模に応じてPEMとアルカリ型の両方が使われています。例えば、安定して99.999%のH₂供給が必要な半導体工場やガラス工場は、大量生産にはアルカリ型+精製装置を、または小型で即導入可能なユニットを求める場合はPEMを選択することがあります。水素化油を使う食品加工工場、フロートガラス工場、超高純度H₂が必要な電子部品メーカーなど、いずれも電解装置を導入しています。過酷な産業環境ではアルカリ型の長期信頼性が魅力的ですが [81]、スペースが限られていたり高純度が必須な環境ではPEMの高純度・コンパクトなスキッドが適しています。
- 熱源との統合: 将来を見据えた用途として、SOECは原子力発電所や集光型太陽熱発電所との連携が検討されています。高温ガス炉や溶融塩タワー型太陽熱発電所は、700℃以上の蒸気をSOECに直接供給し、非常に効率的に水素を生成できます。ヨーロッパ(SOECと研究炉の連携など)や日本でパイロットプログラムが進行中です。これが成功すれば、原子炉が電力需要の少ない時間帯に蒸気と電力をSOECシステムに供給して水素を生産するという新たな分野が開ける可能性があります。
現在の市場リーダーとモデル
電解槽の需要拡大により、世界中の多くの企業が製造拡大に乗り出しています。以下は各カテゴリにおける主要なプロバイダーと注目すべきモデルの一部です:
- アルカリ性メーカー: アルカリ性電解槽分野では、老舗の産業プレーヤーと新規参入者が競争しています。 Thyssenkrupp Nucera(ドイツ、ThyssenkruppとDe Noraの合弁会社)は大規模プロジェクト向けのトップサプライヤーであり、NEOMプロジェクト向けに2GWのアルカリ性電解槽を提供しています。 Nel ASA(ノルウェー)も主要なプレーヤーであり、大気圧アルカリシステムの歴史を持っています。同社のコンテナ型Aシリーズアルカリユニットは多くのプロジェクトで使用されています greenh2world.com。 John Cockerill(ベルギー)は5MWのモジュール式スキッドで加圧アルカリ性電解槽を製造しており、ヨーロッパやアジアのプロジェクトにユニットを供給しています greenh2world.com。米国では、Cummins(Hydrogenics買収を通じて)がHySTAT®モジュール式アルカリ性電解槽ラインを提供しており、信頼性と複数ユニットの連結によるスケーリングの容易さで知られています greenh2world.com greenh2world.com。中国企業は急速に製造量で支配的な地位を築いており、PERIC(国有)やSungrow、LONGi Hydrogen、Tianciなどの民間企業が国内プロジェクト向けに大規模なアルカリ性システムを供給しています(中国は現在、世界の製造能力の約60%を占めています) iea.org iea.org。2023年時点で、アルカリ性技術が市場シェアでリードしており、BloombergNEFによると年間出荷量(容量ベース)の約70~90%を占めていました johncockerill.com。
- PEMメーカー:シーメンス・エナジー(ドイツ)は、著名なPEM製品であるSilyzerシリーズ(Silyzer 200、300など)を展開しており、Shellの製油所でも使用されています。ITM Power(イギリス)のHGASシリーズも有名なPEMシステムで、浄化装置や制御システムを統合したコンテナ型PEM電解装置を提供しています [84]。Plug Power(アメリカ)はPEM市場に積極的に参入しており、米国でギガワット規模の製造を行い、PEM電解装置システムを供給しています(Giner ELXなどを買収)。カミンズもPEM電解装置(カナダの20MW設置例などで使われているHyLYZERシステム)を製造しています。Nelも、産業用や燃料供給用に小型から中型のPEM電解装置を提供しています(米国のProton OnSite買収に由来) [85]。日本では、神戸製鋼所(コベルコ)や東芝が、特にパワー・トゥ・ガスプロジェクト向けにPEMユニットを開発しています。さらに、中国の新興企業もPEM技術に注力しており、例えば上海H-RAYはPEMコスト削減のためのイノベーションを進め、2024年には貴金属使用量削減の進展で評価されました [86]。PEMの設置台数はアルカリ型より少ないものの、多くの欧米および新興メーカーがPEM生産を拡大しており、再生可能エネルギー容量の増加に伴う柔軟な電解装置への高い需要を見込んでいます。
- SOEC開発企業: SOEC分野は、いくつかの専門企業が主導しています。Bloom Energy(米国)は先駆者であり、固体酸化物型燃料電池で知られていますが、その技術を活用して4MWのSOECシステムを開発し、固体酸化物電解の製造ラインを構築中です [87] [88]。Sunfire(ドイツ)もまた先駆者であり、Neste社に2.6MWのSOECを納入し、共電解技術にも取り組んでいます。SunfireはSOECとアルカリ型の両方の製品を提供している点でも独自性があり(アルカリメーカーを買収し、「HyLink」アルカリモジュールとSOECシステムの両方を販売) [89] [90]。Topsoe(デンマーク)は触媒分野の大手で、SOEC設計を開発し、年間500MWのSOEC生産が可能な工場を建設中で、2025年稼働予定です [91] [92]。イギリスでは、Ceres Powerがシェルとパイロットプラントで提携し、スチール支持型セラミックセル技術を活用した固体酸化物型電解装置を開発中です。他にも注目すべき企業として、可逆型SOFC/SOECシステムを研究しているFuelCell Energy(米国)、固体酸化物セル部品を提供するElcogen(エストニア)などがあります。2025年半ば時点で、SOECサプライヤーは最初の商業注文に向けて動き出しており、例えばTopsoeは2025~2026年に最初の大型SOECユニットをプロジェクトに導入することを目指し、Sunfireはフィンランドの製鉄業界向けに10MWのSOECプロジェクトを発表しています。
また、注目すべき新技術としてアニオン交換膜(AEM)電解装置も挙げられます。AEMは、PEMとアルカリ型の利点を組み合わせることを目指しており(アルカリ膜を使用し、液体電解質を使わず、非貴金属触媒を採用)、EnapterやFusion Fuelのような企業がこの分野で小規模ながら成長しています [93]。ただし、AEMはまだ初期段階(小規模導入)にあり、今後5年間の市場の大部分はアルカリ型、PEM型、そしておそらく最初の商業SOECユニットが占めることになるでしょう。
イノベーションと今後の展開(2024~2025年)
電解装置分野は急速に進化しています。最近のイノベーションや今後登場予定の製品には以下のものがあります:
- 高効率設計: スタートアップ企業Hysata(オーストラリア)は、毛細管供給型電解セルを開発し、実験室試験で驚異的な80%効率(LHV)を達成しました [94]。従来のプレートの代わりにスポンジ状の毛細管構造を使用し、抵抗損失を低減しています。この技術は現在スケールアップ中で、実証されれば標準的なPEM/アルカリセルの効率を大きく上回る可能性があります。同様に、SunfireのSOECはすでにパイロットスケールで84%効率(LHV)を達成しており [95]、高温材料のさらなる改良によって電気効率が理論的限界に近づく可能性があります。
- 触媒コスト削減: PEMが貴金属に依存していることから、白金族金属(PGM)の削減または排除に向けた複数の取り組みが進行中です。2023年、Bspkl(英国)という企業が、従来のPEM設計よりもイリジウムと白金の使用量を25分の1に削減した新しい触媒コーティング膜を開発しました [96]。別のイノベーターであるClean Power Hydrogen(CPH2)は、膜なしの電解装置設計を持っています。これは本質的にアルカリ系で混合ガスを生成し、その後水素を分離するもので、高価な膜やPGM触媒を一切使用しません [97]。東芝エネルギーとパートナーのベカートは、PEM電極にナノコーティングを施すことでイリジウム使用量を90%削減する技術を発表しました [98]。これらの進展は、PEMアノードで使用されるイリジウムが極めて希少であるため非常に重要です。IRENAは、イリジウムの世界生産量が削減されなければ、PEMの製造能力が年間約10GWに制限される可能性があると警告しています [99] [100]。触媒の利用効率向上や新規合金・酸化物などの代替触媒の活用によって触媒使用量を大幅に削減することで、PEMコストの低減とサプライチェーンの制約緩和が期待されます。アルカリ技術も触媒の研究開発の恩恵を受けており、アルカリ電極用の新しい耐久性コーティング(例:ニッケル-鉄コーティングや混合金属酸化物)は高電流での効率向上と寿命延長を実現し、アルカリ電解装置が劣化せずにより高負荷で稼働できるようになります。
- 製造の拡大: 需要に対応するため、多くの大規模工場が稼働を開始しています。Nelは2024年にアルカリ電極の全自動生産ラインを開設し、年間数GW規模の生産を目指しています。Topsoeの前述のデンマーク工場(SOECの初期生産能力は500MW/年)は2025年に向けて順調に進んでいます [101]。Cummins/HyLYZERはスペインで新たなPEM電解装置工場(500MW/年の生産能力)を建設中で、カナダでも拡張しています。Plug PowerはニューヨークでPEMスタック生産のギガファクトリーを立ち上げました。これらの施設は規模の経済を促進し、自動化と大量生産によってコスト削減が期待されています。IEAは、工場の生産量増加がすべての電解装置技術の投資コストを削減できると指摘しています [102]。2030年までに、世界で発表された計画は年間160GW超の製造能力に達し、2023年の約25GW/年から大幅に増加します [103] [104]。
- 新規参入とパートナーシップ: 業界では技術を超えた協業が進んでいます。例えば、Thyssenkrupp Nucera(主にアルカリ型に注力)は2024年にフラウンホーファー研究所と提携し、独自の固体酸化物電解装置の開発を発表、2025年までにパイロットを目指しています [105] [106]。これは、既存のアルカリ/PEMメーカーが次世代SOEC研究に投資してリスク分散を図っていることを示しています。一方、従来は燃料電池や他分野にいた企業も電解装置分野に参入しています。例えば、Versogen(米国)やOhmium(米国/インド)は、それぞれAEMとPEMに特化したスタートアップで、新たな資金調達を受けています。大手自動車メーカーや石油・ガス企業も、供給確保のため電解装置への出資や提携を進めています。2024年には、GMとNelが自動車用燃料電池製造技術を活用した低コスト電解装置スタックの共同開発で提携を発表しました。
- 注目すべき今後の製品: 近い将来の例としては、Siemens Energyが1,000cm²超のセル面積を持つ次世代PEMスタックを開発中で、スタックごとの水素生産量を増加させることを目指しており、2025年までにSilyzer 300のアップグレードに搭載される予定です。ITM Powerは、以前の導入から得た知見をもとにPEMスタック(Mk.2)を再設計し、信頼性を向上させており、2024年時点で新しい5MWモジュールのプロトタイプがテストされています。McPhy(フランス)は、20MWクラスの大型アルカリ電解装置(「Augmented McLyzer」)を開発中で、ノルマンディーで100MWのリファレンスプロジェクトが計画されています。Ceres PowerとShellによるインドでのSOECパイロット(1MW規模)では、Ceres独自のセラミックスタックを2025年までに実際の産業環境でテスト予定です。またAEM分野では、Enapterが2023年に量産工場を開設し、標準化された2.5kW AEM電解装置モジュールを生産、これらを大規模システムで数千台集約することを目指しています [107]。
- ソフトウェアとシステムの革新: スタックハードウェアだけでなく、パワーエレクトロニクスやソフトウェア制御の進歩により、性能が向上しています。例えば、より多くの電解装置がスマートな電力管理機能を備え、グリッドサービス(例:周波数調整のための動的な負荷調整)を提供できるようになっています。「デジタルツイン」による電解装置プラントの運用最適化や予知保全も進み、早期に問題を発見してダウンタイムや保守コストを削減しています。また、バランスオブプラントの最適化(より効率的なガスセパレーター、熱交換器、H₂加圧用コンプレッサーなど)も、全体のシステム効率向上とコスト低減に寄与しています。
全体として、2024~2025年は電解装置分野における急速なイノベーションの時期です。効率記録が更新され、設備投資コストも着実に低下しています。米国エネルギー省の専門家がまとめたように、全ての電解装置タイプで「設備コストの削減、効率と性能の向上、寿命の延長」に向けた集中的な研究開発が進められており、実際にその通りの進展が見られます。より耐久性の高い膜、安価な触媒、大規模な生産ライン、そしてよりスマートな設計が実現しています。 [108]
環境への影響と資源利用
グリーン水素推進においては、運転時の排出(再生可能電力で稼働する電解装置は温室効果ガスを排出しません)だけでなく、電解装置の製造・運用に伴う環境負荷も考慮されています。各技術ごとに異なる影響があります。
- 材料資源: アルカリ電解槽は、主要部品に地球上に豊富に存在する材料を使用できるという利点があります。電極は通常ニッケル系(金属酸化ニッケルや鉄合金触媒のコーティングが施されることもあります)であり、セパレーターは現代の設計ではアスベストフリーの多孔質プラスチックやジルコニア系ダイアフラムがよく使われます(古いシステムではアスベストセパレーターが使われていましたが、これは環境および健康上の危険があるため業界では廃止されています)。電解液はKOH(苛性カリ)で、強塩基ですが適切な手順で安全に取り扱うことができ、使用後はリサイクルや中和が可能です。アルカリシステムが低コストである理由の一つは、貴金属を使用しないことです—プラチナやイリジウムは必要ありません。これはまた、アルカリ方式のスケールアップがPEMのような重要原材料のボトルネックに直面しないことも意味します。鋼、ニッケル、苛性カリは容易に入手可能です(ただし、ニッケル採掘にはエネルギー消費や鉱滓など独自の環境問題があります)。アルカリシステムは大量の液体電解液を必要とし、これは定期的に交換されます。使用済みKOH(腐食による汚染物質を含む場合があります)の廃棄は慎重に行う必要がありますが、多くの場合サプライヤーによってリサイクル可能です。
- PEM資源の使用: PEM電解槽は一部の希少材料に依存しています。最も注目すべきは、アノード触媒として使用されるイリジウムです。イリジウムは地球上で最も希少な元素の一つであり、プラチナ採掘の副産物で、年間の世界生産量はわずか数トン程度です。前述の通り、PEM 1MWあたり数グラムのIrを使用する場合、節約しなければ世界のIr供給がPEMの拡大を制限する可能性が懸念されています [109] [110]。そのため、MEAあたりのイリジウム使用量を削減する(例:先進的な触媒や成膜技術)取り組みが持続可能性のために重要です。プラチナ(カソード触媒)も使用されますが、使用量は少なく、プラチナはより入手しやすく(また、燃料電池などからリサイクル可能)です。PEM膜は通常、パーフルオロ化ポリマー(PFSA)であり、基本的にPFAS「永遠の化学物質」の一種です。これらの膜(例:ナフィオン)は非常に優れた性能を発揮しますが、PFASは環境中での残留性や健康リスクの可能性から注目されています。John Cockerillのレポートが強調したように、PEM膜はPFASであり、蓄積して廃棄の問題を引き起こす可能性があります [111] [112]。廃棄時の焼却によってPFASを分解できますが、それには高温かつ専門施設での処理が必要で、排出を防ぐ必要があります。良いニュースとしては、電解槽1台あたりの膜の量はそれほど多くなく(数キログラム)、それでも要素の一つです。PEM用のPFASフリー膜の研究も進められていますが、商業的にナフィオンの性能に匹敵するものはまだありません。良い点として、PEM電解槽は非常に高純度の水素を生成するため、追加の化学的精製工程や関連化学物質が不要です。
- 固体酸化物材料: SOECは、上記とは異なるセラミックおよび金属材料を使用します。電解質はしばしばイットリア安定化ジルコニア(YSZ)であり、基本的にはイットリウムを含む酸化ジルコニウムです。ジルコニウムは希少ではなく(ジルコンとして採掘)、イットリウムも比較的豊富です(しばしばレアアース鉱山から採取されますが、例えばネオジム磁石よりはるかに少量で済みます)。電極には通常、ニッケル(ニッケル-YSZサーメット)や、ストロンチウム添加ランタンフェライトなどのペロブスカイト酸化物が含まれます。ストロンチウムやランタンも採掘が必要な元素です(ランタンは軽希土類ですが、やはりセル1個あたりの必要量は比較的少ないです)。重要なのは、SOECは白金族金属やPFAS膜を必要としないことで、重要材料の観点から大きな利点です。高温合金(インターコネクトプレートや配管用)にはクロムやコバルトが含まれる場合がありますが、これらは高温機器では一般的です。SOECの主な環境上の懸念は、セラミックセルの製造に必要なエネルギーと材料—高温でのセラミック焼結や高精度の確保—および寿命が短い場合、交換品の製造頻度が増えること(つまり長期的には材料使用量が増える)です。SOECスタックのリサイクルはまだ発展途上の分野ですが、理論的にはニッケルなどの金属はリサイクル可能で、セラミックも粉砕できますが、PEMやアルカリ系システムの金属リサイクルほど簡単ではありません。
- 水の使用量: すべての電解装置は水を消費します—おおよそ水9リットルで水素1kgが生成されます(反応式は2 H₂O → 2 H₂ + O₂)。水が不足している地域では、水素を数千トン規模で生産する場合に要因となり得ます。アルカリ型とPEM型は通常、(スケーリングや膜の劣化を防ぐため)純水が必要です。SOECも純水が必要で(蒸気にします)、化学的には水の消費量は同じです。ただし、冷却の必要性は異なる場合があります。アルカリ系は大規模プラントではより多くの冷却水が必要な場合があります(連続運転かつ低温動作のため、余剰エネルギーが低品位熱として放出されるため)、一方SOECは高品位熱をより内部で利用できるかもしれません。海水を使う場合は、通常前段に淡水化装置を設置します—これには独自のエネルギーコストと濃縮廃液が発生しますが、大規模な沿岸プロジェクトでは考慮されています(例えば水素1トンあたり水9トンは、中規模淡水化プラントの水生産量と比べればごくわずかです)。興味深いことに、IEAの調査によると、同じ水素生産量でアルカリ電解は高純度水の使用量がSMR(メタン水蒸気改質)より少ないが、冷却水まで含めると海水の使用量は多くなる可能性があるとされていますが、これらの比較はシステム設計に依存します [113].
- 電力源からの排出: 環境の観点から見ると、電気分解による水素のカーボンフットプリントは、完全に電力源に依存します。再生可能エネルギーや原子力が電力を供給する場合、水素は本質的にゼロカーボンです。しかし、(化石燃料が混在する)グリッド電力が使われる場合、実質的な排出量は大きくなる可能性があります(ただし、多くの地域でグリッドがクリーンになるにつれて減少傾向)。3種類すべての電解槽自体はCO₂を排出せず、副産物として酸素のみを発生します。ただし、製造時には(プラント建設のための鋼やセメントなど)埋込炭素コストがかかります。ライフサイクル分析によると、使用段階が影響の大部分を占めており(電力消費による)、したがって電力の脱炭素化が水素を「グリーン」にする主な手段です。
- 廃棄時とリサイクル: アルカリ電解槽は主に鋼製フレーム、ニッケル電極、一部のプラスチック部品で構成されており、これらはリサイクル可能です(ニッケルや鋼は一般的にリサイクルされる金属です)。KOH電解液は中和できます。PEMスタックには貴重な白金やイリジウムが含まれており、これらの金属を回収するリサイクルプロセス(使用済み触媒コンバーターや燃料電池スタックのリサイクルと同様)がすでに確立されています。これは経済的にも環境的にも良いことです。膜(PFAS)は慎重な廃棄が必要です。SOECスタックは比較的新しいため、まだ確立されたリサイクル方法はありませんが、研究者たちは材料の回収や使用済みセルの安全な処分方法を模索しています。幸いなことに、いずれの電解槽タイプにも鉛や水銀のような有害重金属は含まれていません。主な「有害」要素はPEMのPFASポリマーであり、前述の通り規制の監視下にあります。業界は、これらのポリマーが廃棄時に環境中に放出されないよう、リサイクルまたは適切な焼却処理が行われるように移行していくでしょう。
大まかに言えば、アルカリ電解槽は最もエキゾチックな材料の使用が少なく、PEMは貴金属とPFASの課題があり、SOECは貴金属を回避する一方で先進的なセラミックを使用し、製造により多くのエネルギーを必要とします。良い点として、これらすべての技術は使用時に温室効果ガス排出ゼロの水素サプライチェーンを実現でき、これは化石燃料由来の水素(または最終用途での化石燃料)を代替する場合、非常に大きな環境上の利点となります。専門家は、重要材料(イリジウムなど)の供給管理と持続可能な製造の確保が、現在のメガワット規模から今後数年でギガワット規模へと拡大する際に重要になると強調しています。 [114] [115].
専門家の意見と展望
業界の専門家やアナリストは、これらの技術とその将来について何と言っているのでしょうか?いくつかの洞察に富んだ引用や見解が、その全体像を描くのに役立ちます。
- 万能な解決策は存在しない: 主要な電解槽サプライヤーであるJohn Cockerillによる最近の分析では、「すべての側面で優れた性能を発揮する単一の電解槽技術は存在しない」 [116]と結論付けられています。最適な選択肢は、コスト、効率、拡張性、純度など、用途や優先事項によって異なります。例えば、初期投資コストの低さと実績ある信頼性が最重要(大規模な化学プラントなど)であれば、アルカリ型が好まれるかもしれません。スペースが限られていたり、電力が変動する場合はPEMが適している可能性があります。これは、各技術にはそれぞれの得意分野があることを示しており、多くの専門家はすべての技術を組み合わせたポートフォリオが必要になると考えています。John Cockerillのレポートでも、「アルカリ型は…ニーズの変化に応じて容易に拡張でき、ほとんどの産業に対して堅牢で信頼性の高い出力を提供できる一方、輸送などの特殊分野ではPEMの純度やコンパクトさがより適している場合がある」 [117] [118]と指摘されています。
- 効率性の重要性について: Bloom Energy(SOECを製造)のCTOであるDr. Ravi Prasherは、経済性において効率がいかに重要かを強調しています。「水素を製造するために電解槽が必要とする電力量が、水素製造コストを決定する最も支配的な要因となる。そのため、効率…が最も重要な指標となる。」 [119]。これは、資本コストが下がってきている一方で、運用コスト(電力消費によって左右される)が主要な差別化要因になるという専門家の共通認識を反映しています。特にプロジェクトが拡大し、電力が大きなコスト要因となる場合に顕著です。彼のコメントは、Bloomが高効率SOECを実証した際のもので、4MWシステムが1kgあたり37.7kWh(蒸気を利用しているため非常に低い)で水素を生産しており、部分負荷でも他の技術より高効率であると述べています [120] [121]。このような成果は、技術革新によって水素コストが大幅に削減できるという楽観論を後押ししています。
- 柔軟性とエネルギー貯蔵: 水素を再生可能エネルギーと統合することに関連して、BloomのCEOであるKR Sridharは、エネルギー貯蔵における電解装置の役割を強調しました: 「水素は断続的かつ抑制されたエネルギーの貯蔵や、産業用エネルギー利用の脱炭素化に不可欠です。商業的に実現可能な電解装置こそが、エネルギー貯蔵のパズルを解く鍵です。」 [122]。彼は、SOECのような先進的な電解装置が「本質的に優れた技術的・経済的利点」を長期的にもたらすと主張していますが、これはもちろんSOEC支持者の視点です。それでも、多くのエネルギー専門家は、水素(余剰再生可能エネルギーが利用可能なときにどの電解技術でも生産されるもの)が、季節的な貯蔵や削減が困難な分野の要となると見ています。
- 産業の拡大と投資: IEA事務局長のファティ・ビロルは、2023年末に「新規プロジェクトの増加は、低排出水素生産の開発に対する投資家の強い関心を示している」と述べましたが、多くの発表済みプロジェクトが実際に建設段階に進む必要があるとも警告しました [123] [124]。彼は、電解装置への投資に自信を持たせるためにはクリーン水素の需要が確実になる必要があると強調しました [125]。これはより広範な専門家の懸念、すなわち政策と市場の支援が技術と歩調を合わせて成長しなければならないという点を示しています。2025年時点で、欧州、北米、中国などの政府は、コストギャップを埋めて導入を促進するためのインセンティブ(税額控除、補助金、水素購入契約)を展開しています。これらの施策は、業界リーダーの目には、現在の数百MW規模から気候目標達成に必要な年間数十GW規模への電解装置の展開拡大に不可欠です [126] [127]。
- 新技術に対する見解: 学界の一部専門家は、AEMやSOECのような新技術は魅力的だが、利用可能な技術の導入を妨げるべきではないと警鐘を鳴らしています。カリフォルニア大学アーバイン校のJack Brouwer教授(⽔素エネルギー研究者)は、2024年のパネルディスカッションで「今は実証済みのPEMやアルカリを“導入、導入、導入”すべきだ」と述べました(次世代技術の研究開発も続けつつ)—なぜなら、規模を拡大することでコストが下がり、実践を通じて学ぶことができるからです(イベントでの発言を要約)。この現実的な見方は一般的であり、手元にある商用ツール(AWE/PEM)を使って排出削減を始めつつ、新技術も将来のために育てていくべきだとされています。
- ヨーロッパのリーダーシップとエネルギー安全保障: Sunfire社CEOのNils Aldag氏は、MultiPLHY SOECプロジェクトについて語り、「MultiPLHYのような画期的な水素プロジェクトが、クリーンテクノロジー分野でヨーロッパの世界的リーダーとしての地位を確立する基盤を築いている」と述べました。 [128]。これは、SOECのような高効率電解槽やギガワット級アルカリプラントなど、電解槽分野で最先端を追求することが、気候目標の達成だけでなく、エネルギー転換のための国内産業の構築にもつながるというヨーロッパの意識を反映しています。彼のヨーロッパの地位への強調は、電解槽プロジェクトが国際的な技術的誇りや競争の源であることを示しています。
結論として、専門家の間では各電解槽タイプにはそれぞれ独自の強みがあり、イノベーションの急速な進展は良い兆候だと認識されています。コンセンサスとしては、あらゆる電解槽技術がさまざまな需要に応えるために必要だというものです。すなわち、バルクで低コストの水素にはアルカリ、動的かつ高純度用途にはPEM、高効率統合システムにはSOECが適しています。現在の焦点は、製造規模の拡大、コスト削減、耐久性の向上にあります。IEAが簡潔に述べているように、継続的なイノベーションによって「全体的な設備投資コストを削減する必要があるが、その際には寿命や効率とのトレードオフも考慮しなければならない」 [129]。これらの要素のバランスを取ることが重要です。
最近のニュースと動向(2024~2025年)
過去2年間で、水素電解槽プロジェクトやパートナーシップの発表が加速しています。ここでは、注目すべき最近の動向を紹介します:
- 記録的なプロジェクト: 2023年半ば、中国のSinopecは新疆で世界最大のグリーン水素プラントを稼働開始しました――前述の通り、260MWのアルカリ電解装置アレイです。2024年末までにこのプラントは生産を増強し、中国の野心と学習曲線上の課題の両方を浮き彫りにしました(報道によると、システム調整のため当初は稼働率が約30%にとどまっていました) [130]。一方、ヨーロッパでは大規模プロジェクトが節目を迎えました。2024年7月、Shellはドイツで100MWのRefhyne II PEM電解装置の最終投資決定を下しました(2027年稼働予定) [131] [132]。同月、EUグリーン水素バンクが初のオークションを開催し、300万トンの水素(H₂)を支援、プロジェクトに長期的な価格支援を提供しました [133] [134]――これは大規模電解装置導入のためのオフテイク(引き取り)を確保する政策イノベーションです。
- 官民パートナーシップ: 大手石油・ガス会社が電解装置メーカーと提携しています。例えば、BPとThyssenkrupp Nuceraは2024年に、BPの製油所で500MWの電解装置を導入する協業を発表しました。ExxonMobilはElectric Hydrogen(先進的PEMシステムを開発する米国スタートアップ)に投資し、産業用水素の低コスト化に取り組んでいます。また注目すべき上流の動きとして、サウジアラムコは2025年に韓国のベンチャー企業に投資し、低コスト水素のための固体酸化物電解(SOEC)を開発、製油所の熱利用と結びつけています。
- 製鉄におけるSOEC: オーストラリアでCSIROとBlueScope Steelによる画期的なパイロットが開始され、製鉄所の廃熱を利用して1,000時間にわたりチューブラー型SOEC電解装置で水素を製造しました [135]。この2024年末の試験は効率性と耐久性の両方を実証し、製鉄業界でのSOECの実地試験としては初期の事例となりました(将来的には水素で石炭の代わりに鉄鉱石還元が可能になる可能性があります)。ヨーロッパでは、Salzgitter SteelがSunfireと協力し、2025年までにSOECユニットを製鉄所に導入する計画で、SalzgitterのSALCOSプロジェクトの一環として製鉄の脱炭素化を目指しています。
- 電力会社が水素事業に参入: 発電事業者は、余剰電力を貯蔵し新たな収益源を生み出すために電解装置に注目しています。2024年、米国の大手再生可能エネルギー開発会社であるNextEra Energyは、テキサス州で抑制された風力・太陽光を利用し、近隣産業向けにグリーン水素を生産するため、数百MW規模の電解装置を導入する計画を発表しました。同様に、フランスのEDFは、原子炉と30MWのPEM電解装置を組み合わせ、肥料生産向けに水素を供給するプロジェクトを開始しました。興味深いことに、原子炉の出力を調整せず安定した原子力発電を利用しており、ベースロード発電事業者でさえ水素をオフテイク先と見なしていることを示しています。
- 水素ハブと資金調達: 米国の「水素ハブ」プログラム(2021年インフラ法により支援)は、2023年末に地域コンソーシアムへ約80億ドルを交付し、その多くが大規模な電解装置の導入を含んでいます。例えば、カリフォルニアの水素ハブは約150MWの電解装置(PEM型とアルカリ型の両方)を計画し、輸送用燃料を供給します。中西部のハブは原子力発電を水素製造に利用(おそらくPEMまたはアルカリ技術)、テキサスのハブは石油化学用途の水素製造に大規模な風力・太陽光を統合します。これらのハブは電解装置メーカーへの発注を促し、さまざまな条件下で異なる技術を実証する場となります。
- 新製品の出荷: 企業動向では、Nel Hydrogenが2024年に新型全自動アルカリ電解装置ラインの初号機を20MWプロジェクト向けに納入し、製造コストを最大40%削減できる能力を示しました。Plug Powerは、5MWのモジュラー型PEM電解装置スキッド(「ML 5」と呼ばれる)を発表し、100MW規模のプロジェクト向けに(20台設置することで)簡単に導入できることを狙っています。McPhyは大口受注を受けて、フランスでアルカリ型とAEM型の両電解装置を製造するギガファクトリーの建設を開始しました。また、Enapterは2023年にドイツの新工場から量産型AEM電解装置モジュールの出荷を開始し、数千台単位でスケーラブルに設置することを目指しています。
- 安全性と標準化: 成長とともに、安全性と標準化への注目も高まっています。2024年、国際電気標準会議(IEC)は電解装置の安全基準を改訂し、電気的絶縁から水素漏れ検知までを網羅した基準を発表、メーカーが採用を進めています。また、アジアの大規模プロジェクトで、アルカリ電解装置の一部モジュールがシール不良による苛性ソーダ漏れで停止する事故も発生しました [136]。これは、より多くの初の大規模プラントが稼働する中で、堅牢なエンジニアリングとベストプラクティスの共有の必要性を強調しています。業界はこれに対応し、水素協議会の下に新たな安全フォーラムを設立し、得られた教訓の普及に努めています。
- 市場の動向: 2025年までに、一部の地域(例:中国)で製造のやや過剰供給が見られ、実際に価格の下落を促しました。IEAは、世界の製造能力(2023年で25GW/年)が現在の導入量(約1GW/年)を大きく上回っていると指摘しています。 [137] [138]。これにより価格競争が激化し、業界の統合も進んでいます。例えば、2025年初頭には大手石油・ガス機器企業が小規模な電解槽スタートアップの1社を買収し、自社のポートフォリオに統合するという噂もあります。
これらすべての動きが示しているのは一つのことです。電解槽技術が研究室やパイロット段階から本格的な産業導入へと移行しつつあるということです。 政府が支援し、大企業が投資し、エンジニアリング上の課題も一つずつ解決されています。導入が拡大するにつれ、各技術の役割もさらに学習・洗練されていくでしょう。
結論
PEM、アルカリ、固体酸化物電解槽を並べて比較すると、それぞれに独自の利点があることが明らかです:
- アルカリ電解は低コストで実績ある信頼性を持ち、スペースと安定した運転が確保できる大規模水素製造に最適です。
- PEM電解は柔軟性、迅速な応答、高純度水素を提供し、可変的な再生可能エネルギーとの統合や、コンパクトで高性能なシステムが求められる用途に最適です。
- 固体酸化物電解は最高効率と熱源との統合の可能性を持ち、耐久性とコストがさらに改善されれば、産業分野での水素製造を革新する可能性があります。
どれを選ぶかは、プロジェクトの詳細――電源、必要な水素の量と純度、予算、運転のダイナミクス――によって決まります。ある業界関係者が賢明に述べたように、「用途によって最適なものは異なり、電力コスト、圧力要件、設置面積、その他の要素が決定要因となる」 [139] [140]。
心強いのは、3つの技術すべてが急速に進歩していることです。 R&Dや規模の経済のおかげでコストは下がり、効率は徐々に向上し、PEMのより優れた触媒、より応答性の高いアルカリシステム、長寿命のSOECスタックなど、過去の制約を克服する新しいソリューションも登場しています。特に2024~2025年は、数多くの「次世代」コンセプトの最初の実装とイノベーションの活発化が見られました。
専門家は、グリーン水素がネットゼロ経済において重要な役割を果たすと考えています。そして、それを実現するには、用途に合った適切な電解装置の導入が不可欠です。アンモニア肥料用に水素を大量生産するアルカリ型ユニット、風力発電所に連動して稼働するPEMユニットの列、製油所で廃熱を利用する高温SOECなど、それぞれが他に選択肢の少ない分野(重工業、化学、長距離輸送など)の排出削減に貢献しています。
今後数年で、世界的に電解装置の容量が大幅に拡大すると予想されます。現在の総設置容量は約1GWですが、2030年までに数百GWが計画されています [141] [142]。この拡大は政策や民間投資によって支えられ、さらなる改良を促進します。将来的には、PEMとアルカリ型を組み合わせて異なる運転範囲をカバーしたり、SOECでベースライン、PEMでピーク負荷を担うなどのハイブリッドシステムも登場するかもしれません。技術間の協力と健全な競争が効率向上とコスト削減を促し、水素経済全体に恩恵をもたらします。
まとめると、PEM、アルカリ型、SOEC電解装置はいずれも重要な役割を担っています。この対決の「勝者」は、他の技術を打ち負かす一つの技術ではなく、クリーン水素を生産するための多様なソリューションを得る気候や産業です。水素専門家のポール・マーティン氏が冗談めかして言ったように、どの電解装置が一番良いかを尋ねるのは、「一番良い道具は何か:ハンマー、レンチ、それともドライバー?」と聞くようなものです。用途によって異なり、道具箱が充実しているのが一番です。継続的なイノベーションと導入により、これらの電解装置技術はグリーン水素の転換をニッチから世界を変えるソリューションへと推進していくでしょう。
出典:
- 米国エネルギー省 – 水素製造:電気分解(電解装置の仕組み、運転条件) [143] [144]
- 国際エネルギー機関(IEA) – 「電解装置」2024年レポート(技術の現状、コスト、効率、プロジェクト) [145] [146]
- Electric Hydrogen Co. – ホワイトペーパー 2024(PEMとアルカリの効率およびコストの分析) [147] [148]
- John Cockerill Hydrogen – 技術概要 2024(アルカリとPEMの比較、市場シェア、材料) [149] [150]
- Hydrogen Insight – Leigh Collins, 「世界最大の固体酸化物型電解槽が設置」(SOECの効率とコスト優位性) [151]
- Hydrogen Tech World – 「ブルーム・エナジー、NASA SOECで水素生産開始」(ブルーム4MW SOECの性能と専門家のコメント) [152] [153]
- EnergyTech Magazine – 「サンファイア、Nesteに2.6MW SOECを設置」(SOECの運転詳細とSunfire CEOのコメント) [154] [155]
- ロイター – Andrew Hayley, 「シノペック初のグリーン水素プラントが生産開始」(260MWアルカリプロジェクトの詳細) [156] [157]
- IEA – イノベーションインサイト(イリジウム削減、新しい電解槽効率記録、東芝触媒) [158] [159]
- Stargate Hydrogen – 「PEMとアルカリ電解槽の比較」ブログ(長所・短所の分かりやすい解説) [160] [161]
- Shanghai H-Ray – 2024年ニュースリリース(PEMコスト削減と展望) [162]
References
1. www.energy.gov, 2. www.energy.gov, 3. www.energy.gov, 4. stargatehydrogen.com, 5. stargatehydrogen.com, 6. www.energy.gov, 7. www.energy.gov, 8. stargatehydrogen.com, 9. stargatehydrogen.com, 10. www.energy.gov, 11. stargatehydrogen.com, 12. stargatehydrogen.com, 13. www.energy.gov, 14. www.energy.gov, 15. www.energy.gov, 16. www.energy.gov, 17. www.energy.gov, 18. hydrogentechworld.com, 19. www.energy.gov, 20. eh2.com, 21. eh2.com, 22. eh2.com, 23. eh2.com, 24. hydrogentechworld.com, 25. hydrogentechworld.com, 26. www.iea.org, 27. www.iea.org, 28. hydrogentechworld.com, 29. www.energy.gov, 30. stargatehydrogen.com, 31. www.energy.gov, 32. stargatehydrogen.com, 33. www.energy.gov, 34. www.energy.gov, 35. www.iea.org, 36. www.iea.org, 37. www.iea.org, 38. www.energy.gov, 39. www.energy.gov, 40. h-raypem.com, 41. www.energy.gov, 42. www.energy.gov, 43. www.iea.org, 44. www.energy.gov, 45. stargatehydrogen.com, 46. www.greenh2world.com, 47. www.greenh2world.com, 48. johncockerill.com, 49. stargatehydrogen.com, 50. stargatehydrogen.com, 51. www.energy.gov, 52. stargatehydrogen.com, 53. stargatehydrogen.com, 54. stargatehydrogen.com, 55. stargatehydrogen.com, 56. www.energy.gov, 57. www.energy.gov, 58. hydrogentechworld.com, 59. hydrogentechworld.com, 60. stargatehydrogen.com, 61. stargatehydrogen.com, 62. johncockerill.com, 63. johncockerill.com, 64. johncockerill.com, 65. stargatehydrogen.com, 66. hydrogentechworld.com, 67. stargatehydrogen.com, 68. stargatehydrogen.com, 69. johncockerill.com, 70. johncockerill.com, 71. johncockerill.com, 72. johncockerill.com, 73. www.iea.org, 74. www.iea.org, 75. www.iea.org, 76. www.iea.org, 77. www.reuters.com, 78. www.reuters.com, 79. stargatehydrogen.com, 80. stargatehydrogen.com, 81. johncockerill.com, 82. www.iea.org, 83. www.iea.org, 84. www.greenh2world.com, 85. www.greenh2world.com, 86. h-raypem.com, 87. www.iea.org, 88. www.iea.org, 89. www.greenh2world.com, 90. www.greenh2world.com, 91. www.iea.org, 92. www.iea.org, 93. www.iea.org, 94. www.iea.org, 95. www.iea.org, 96. www.iea.org, 97. www.iea.org, 98. www.iea.org, 99. johncockerill.com, 100. johncockerill.com, 101. www.iea.org, 102. www.iea.org, 103. www.iea.org, 104. www.iea.org, 105. www.hydrogeninsight.com, 106. www.thyssenkrupp-nucera.com, 107. www.iea.org, 108. www.energy.gov, 109. johncockerill.com, 110. johncockerill.com, 111. johncockerill.com, 112. johncockerill.com, 113. horizoneuropencpportal.eu, 114. johncockerill.com, 115. johncockerill.com, 116. johncockerill.com, 117. johncockerill.com, 118. johncockerill.com, 119. hydrogentechworld.com, 120. hydrogentechworld.com, 121. hydrogentechworld.com, 122. hydrogentechworld.com, 123. www.iea.org, 124. illuminem.com, 125. carboncredits.com, 126. www.iea.org, 127. www.iea.org, 128. www.energytech.com, 129. www.energy.gov, 130. energynews.biz, 131. www.reuters.com, 132. www.refhyne.eu, 133. www.iea.org, 134. www.iea.org, 135. www.csiro.au, 136. www.hydrogeninsight.com, 137. www.iea.org, 138. www.iea.org, 139. johncockerill.com, 140. johncockerill.com, 141. www.iea.org, 142. www.iea.org, 143. www.energy.gov, 144. www.energy.gov, 145. www.iea.org, 146. www.iea.org, 147. eh2.com, 148. eh2.com, 149. johncockerill.com, 150. johncockerill.com, 151. hydrogentechworld.com, 152. hydrogentechworld.com, 153. hydrogentechworld.com, 154. www.energytech.com, 155. www.energytech.com, 156. www.reuters.com, 157. www.reuters.com, 158. www.iea.org, 159. www.iea.org, 160. stargatehydrogen.com, 161. stargatehydrogen.com, 162. h-raypem.com